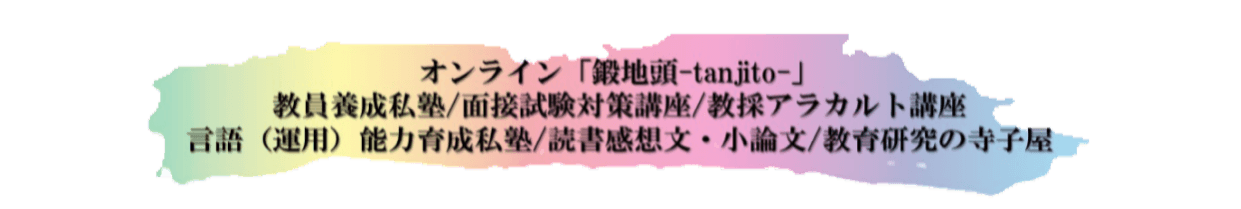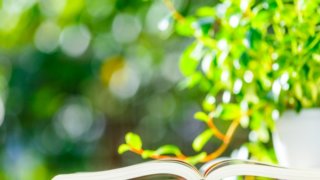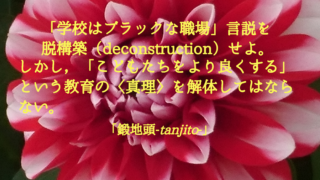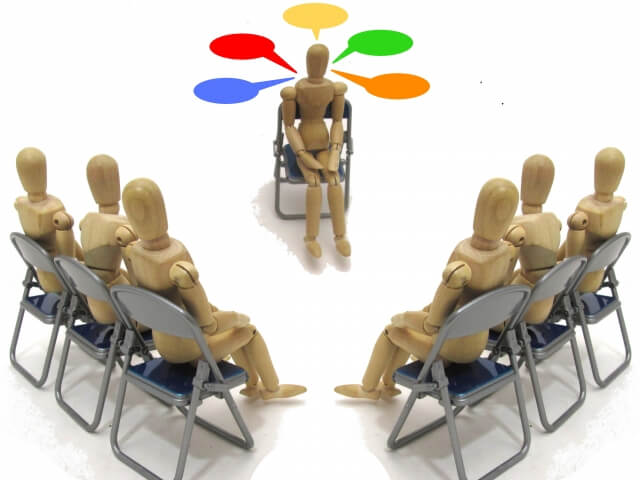 「鍛地頭-tanjito-」の国語教育論
「鍛地頭-tanjito-」の国語教育論 BLOG
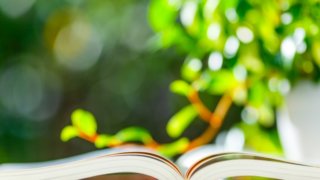 保護者が語る教育論
保護者が語る教育論 「学ぶこと」,「まねること」,「参加すること」
見たり聞いたりしたことを,そのまま他者に伝えることは,「まねぶ(まねる)」ことではなく,文字どおり「盗む」ことで,「横流し」に過ぎません。それでは,相手の関心・感動も,納得も得られません。「学ぶ意欲」を持って,「学ぶ姿勢」で,問題解決に向け,「社会の文化的実践に参加すること」,それが真の〈学び〉なのかもしれません。
 「鍛地頭-tanjito-」の〈教員採用試験論〉
「鍛地頭-tanjito-」の〈教員採用試験論〉 「敵/味方」の思考を止揚(aufheben)せよ!!-一元論的「保護者-教員(学校)等」関係論-
「鍛地頭-tanjito-」の「保護者-教員(学校等)」関係論の第3弾。歯に衣着せぬ筆致で書き下ろしました。保護者と教員(学校等)とのトラブルの根源を物心二元論に求め,一元論的視点によって,乳幼児・児童・生徒を中心に据えた円満な関係構築の在り方について論じます。塾長の長い教職経験の中から選定した小話は衝撃的です。
 教育経験者が語る教育論
教育経験者が語る教育論 青天の霹靂 ― 一人ひとりが輝く育児 ― 〔第1回〕
青天の霹靂!! 急遽2週間後に当塾の育児コースが講座を展開しなければならなくなりました。テーマは〈言葉〉。人の営為は〈言葉〉抜きでは成り立ちません。育児も同様です。保護者の言語能力と言語運用能力が豊かであれば,こどものこれらの能力も豊かに育っていきます。感性・情緒が豊かであることもこれらの能力によるのです。
 保護者が語る教育論
保護者が語る教育論 「ありがとう」は〈有り難い〉自他の存在を認める〈有り難い〉言葉
みなさんは,1日に何度「ありがとう」と言っていますか? みなさんは,普段,どのような時に,「ありがとう」と言いますか? また,「ありがとう」と言われた時,どのような気持ちになりますか? 「ありがとう」に込められる想いや,言葉の〈有り難さ〉について語りました。
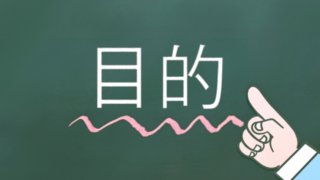 旧「鍛地頭-たんじとう-」の教育論〔リメイク版〕
旧「鍛地頭-たんじとう-」の教育論〔リメイク版〕 「目的」と「目標」
「目的」と「目標」。同一の概念ではありません。混同すると,「「夢」あって,「成功」なし。」になりませんか? 平昌オリンピックに浸り,吉田松陰の「夢泣き者に理想なし」の名言を想起しながら,そのようなことを考えてました。自分の人生にとっての「目的」は何か,それに到達するための「目標」は何か。〈生きる〉ために考えてみました。
 旧「鍛地頭-たんじとう-」の教育論〔リメイク版〕
旧「鍛地頭-たんじとう-」の教育論〔リメイク版〕 バレンタインデーのレストラン
今日はバレンタインデー。雰囲気の良い素敵なレストランで,美味しいお料理に舌鼓を打ちながら,熱く語り合っておられるハッピーな方々もおいでになるのでは? うちの塾長,ああ見えて美味しいレストランをたくさん知っているのですが,実際,ねらいはお料理だけではなかったのです。塾長独自の経営理論は美味しいお店の秘密にあったのです。
 保護者が語る教育論
保護者が語る教育論 人と人とをつなぐ「あいさつ」―〈つながり〉を求めて―
みなさんは,「あいさつ」をされていますか? 家庭,地域,学校,会社など,あらゆる場で「あいさつ」は交わされると思います。大人が自然と「あいさつ」をしていれば,こどもも自然と「あいさつ」を行います。「あいさつ」は,「包み隠さない自分(の気持ち)」を相手に届けることを表現し,自ら他者に〈つながり〉を求める行為なのです。
 旧「鍛地頭-たんじとう-」の教育論〔リメイク版〕
旧「鍛地頭-たんじとう-」の教育論〔リメイク版〕 教師教育 他者をみる〈チカラ〉―その重要性について―
看護・介護界ではよくご存じの「目を開けて,私をもっとよく見て」という老人のメモ。本ブログの筆者の眼差しは,このメモから世界中のこどもたちへと注がれ,老若男女問わず,「人」として同定されていきます。そして,他者の心の中を理解するためには,自己内のもう一人の自己と〈対話〉する必要があることに気づいていくのです。
 保護者が語る教育論
保護者が語る教育論 地域が連携する子育て支援
娘が通う保育所で開催された「運動会」。そこで感じた「地域」とのつながり。昔は当たり前であったであろう,「地域でこどもを育てる」という光景を,久しぶりに目の当たりにしたと実感いたしました。核家族化が進行を続ける中で,こどもを取り囲む地域の方々の存在が大きいのではないでしょうか。
 「鍛地頭-tanjito-」の教育論
「鍛地頭-tanjito-」の教育論 《続編》周利槃特とトイレの神様が教える日本の学校で児童生徒が掃除をするわけ
本ブログは,「学校掃除の意義について」の第二弾です。今回と次回にわたって,フォークロア(民俗学)的な視点及び私の高校教師時代の実践とその分析に基づき,日本(東アジア,仏教圏)で児童生徒が学校掃除を行う理由について,当塾の持論を述べたいと思います。さあ,前回の「周利槃特」は,今回,どのようにかかわってくるのか?
 保護者が語る教育論
保護者が語る教育論 朝の気分で1日が決まる
子どもの存在は,とても大きいです。大人(親)の気持ちを敏感に察知して,同じような気分になっていることはありませんか? 笑顔で気持ちよく1日のスタートができたら,大人もこどもも明るく過ごせることが多いように感じます。そんな我が家の合言葉は,「今日も元気に頑張るぞ!! おぉ~!!」。
 「鍛地頭-tanjito-」の教育論
「鍛地頭-tanjito-」の教育論 教師教育「先生,あの先生,授業に自信がないん?」―学習指導と生徒指導とは車の両輪の関係—
どの児童生徒も授業内容を理解したいのです。どの児童生徒も教職員をしっかりと見つめています。そして,学習指導とは生徒指導であり,生徒指導とは学習指導であることをよく知っています。学習指導も生徒指導も一人ひとりの児童生徒を大切にすることから始まるのです。塾長の教育実践における衝撃的な一コマがそれらのことを教えてくれます。
 保護者が語る教育論
保護者が語る教育論 プロフェッショナルの意識を持ちましょう!!
「プロフェッショナル」を略して,「プロ」と言いますが,一般的には,「プロとはその道でお金をもらって生活をしている者」と定義されています。実は,「プロ」と呼ばれることに,経験年数は含まれていないのです。どの職種においても,初めてその場に立った時から「プロ」なのです。それは,「親」という立場でも同じだと考えています。
 「鍛地頭-tanjito-」の〈教員採用試験論〉
「鍛地頭-tanjito-」の〈教員採用試験論〉 学習規律の確立には学習者の内発的動機づけが肝心!!
本ブログは「「鍛地頭-tanjito-」の教育論」(「実践編」)の第2弾。今回は「学習規律」に焦点を当て,塾長の教育実践を披瀝しながら,「学習規律」と「外発的動機づけ」・「内発的動機づけ」との連関性について語ります。一般の方にもお読みいただける内容で,教員採用候補者選考の受験用参考書の体裁も取ります。お得情報満載です。
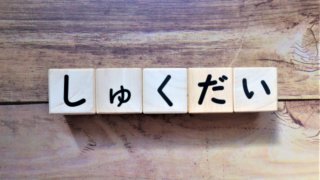 「鍛地頭-tanjito-」の〈教員採用試験論〉
「鍛地頭-tanjito-」の〈教員採用試験論〉 提出物の提出状況から氷山の水面下部を見よ。〔改訂版〕
本ブログは「「鍛地頭-tanjito-」の教育論」に新設したカテゴリー「実践編」の第1弾,「提出物の指導」に加筆したリライト版です。提出物の指導だけではありませんが,「氷山の水面下部」を見ることから〈ホンモノの指導〉が始まります。しかも,それは組織的でなければなりません。その組織性の重要性について再度訴えました。
 「鍛地頭-tanjito-」の〈教員採用試験論〉
「鍛地頭-tanjito-」の〈教員採用試験論〉 教員採用試験で「場面指導」を「バメンシドウ」と思うな!!
「定式化した戦略的な思考で突っ走るな!!」「「まずは方法ありき」と言った考え方を捨てろ!!」本ブログは,昨今,教員採用試験において比重を増してきた「場面指導」を日常の学校教育の文脈に位置付け再構築し,教職員の乳幼児・児童・生徒に向ける熱き〈教育愛〉から捉え直した教育論です。場面指導対策言説から受験主体を解放に導きます。
 「鍛地頭-tanjito-」の教育論
「鍛地頭-tanjito-」の教育論 〈いのち〉の大切さを知る体験講座
咄嗟の出来事(例:緊急事態への偶発的な直面)に対しての「対処・対応する能力」と,身の回りに生起する数々の問題を発見・解決する「問題解決能力」とは似て非なるものです。こどもたちに適切であると思われる言動等を求める前に,まずは私たち大人が誤った知識の習得や指導及び教育を行わないことが重要です。そのためには,……。
 「鍛地頭-tanjito-」の〈教員採用試験論〉
「鍛地頭-tanjito-」の〈教員採用試験論〉 模擬授業は「パフォーマンス」では乗り切れない!!
「模擬授業はパフォーマンスですよね?」―教員採用試験が迫った受験者の弁である。正直,驚いた。「今までどこで何を学んで来たのだ!」全ての受験者がこうした状況ではないと願う。そこで,模擬授業を媒介に軽い当塾の〈授業論〉を打つことにした。当塾の〈授業〉に対する〈教え〉も混ぜてある。教員採用試験受験者には必読していただきたい。
 「鍛地頭-tanjito-」の教育論
「鍛地頭-tanjito-」の教育論 お手伝いからの〈学び〉の発展―「自己有用感」と「食育」―
今夏,夏季休業中に取り組んだ「お手伝いお当番さん」の第2弾です。評価の視点を加えた「当番表」の修正からこどもたちが獲得した〈新しい学び〉への「自己成長」の過程を語ります。所謂「お手伝い」,然れど,「お手伝い」。「お手伝い」を通してこどもたちが得た「自己有用感」を誘ったものは,何と我が家の「食育」だったのです。
 「鍛地頭-tanjito-」の営業活動
「鍛地頭-tanjito-」の営業活動 自己内のパラダイムシフトを生起する教員養成私塾
教員採用二次試験直前の当塾による面接試験対策講座の一幕。受講者様から思いもよらない有り難いお言葉を賜り,感激に咽ぶ当塾のスタッフ。「まず乳幼児・児童・生徒ありき」との当塾の基本理念が無意識裡に形成されていた受講者様の心を呼び起こしたのです。「コロンブスの卵のようなパラダイムシフトが起こった」瞬間でした。
 「鍛地頭-tanjito-」の営業活動
「鍛地頭-tanjito-」の営業活動 〈ホンモノの教員〉を目指しませんか?
当塾「鍛地頭-tanjito-」は広島県を拠点にオンラインで幅広く活動を展開する〈ガイダンス・カウンセリング〉の相談ルームを持った新型の〈Private school(私塾)〉です。主な業務の一部門である【教員採用試験合格道場―オンライン教員養成私塾「鍛地頭-tanjito-」】が新規塾生を募集します。
 「鍛地頭-tanjito-」の教育論
「鍛地頭-tanjito-」の教育論 夏休みに家族で取り組む「お手伝い当番表」
先日,「これは!!」というFacebookの記事に邂逅し拝読しました。それは,しみずよしみさんが投稿されていた「家族で取り組む家事当番表」の記事です。記事内の「みんなのおうち」という表現にもグッと心を摑まれました。こどもの成長を願い,〈家族みんなのいえ〉の在り方について,お手伝いを通した実践と考察を試みました。
 塾長の述懐
塾長の述懐 「思いやり」と温情主義―ポストモダン終焉期の実相〔12-2〕
「塾長の述懐」シリーズの第12弾です。今回はポストモダン終焉期の実相として,現行の大学入試を採り上げながら,〈言語能力〉及び〈言語運用能力〉の低下がもたらす弊害について,視点論的な見方から,温情主義(パターナリズム)及び「思いやり」にまで言及してみました。一元論的トランスモダンの時代に求められる人材の前段階を語ります。
 副塾長のつぶやき
副塾長のつぶやき 西日本豪雨災害から1年-それぞれの想いを乗せて
 塾長の述懐
塾長の述懐 ポストモダン終焉期の実相〔12-1〕
「塾長の述懐」シリーズの第12弾です。今回はポストモダン終焉期の実相として,現行の大学入試を採り上げながら,〈言語能力〉及び〈言語運用能力〉の低下がもたらす弊害について,視点論的な見方から,温情主義(パターナリズム)及び「思いやり」にまで言及してみました。一元論的トランスモダンの時代に求められる人材の前段階を語ります。
 こどもを伸ばす魔法の言葉
こどもを伸ばす魔法の言葉 すかさず! 大きな声で! スマイル!!
 塾長のつぶやき
塾長のつぶやき 副塾長,西日本豪雨により被災!! -「思い出」が〈思い出〉になってしまった-
 特別支援教育(療育)
特別支援教育(療育) 個に応じた発達支援―ペアレント・トレーニングを採り入れてみて―
 ランキング(当塾比)
ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.6.16〕
 ランキング(当塾比)
ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.6.9〕
 塾長のつぶやき
塾長のつぶやき 「The パクるな!!」-オリジナリティーを求めて-(第6回)
「The パクるな!!」の第6弾。教師に求められるオリジナリティーを探し求め,今回はその根底となる概念「オリジナリティーを創造する視点形成の在り方」を当塾なりに論じます。愈々,C・オットー・シャーマーの「U理論」を援用した当塾独自のオリジナリティー形成論に向け,第1歩を踏み出しますので,是非ご一読ください。
 ランキング(当塾比)
ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.6.2〕
 塾長の述懐
塾長の述懐 「地頭」を「鍛」えれば受験はクリアできる〔11〕
 ランキング(当塾比)
ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.5.26〕
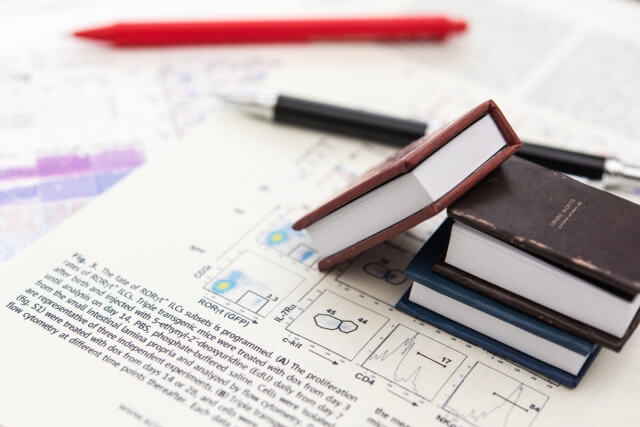 塾長の述懐
塾長の述懐 「受験脳(テクニック)」育成の弊害と「鍛地頭」の必要性について〔10〕
 ランキング(当塾比)
ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.5.19〕
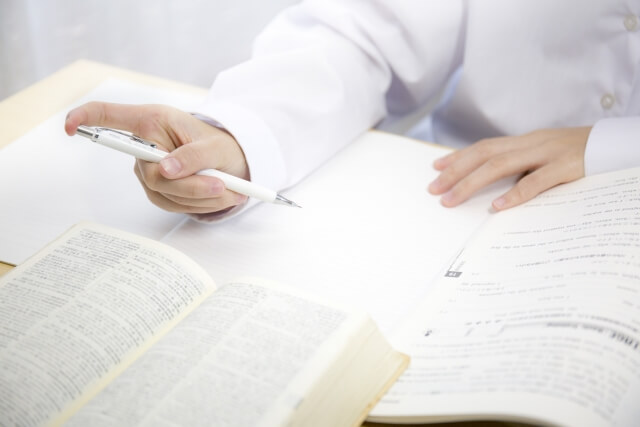 塾長の述懐
塾長の述懐 塾長の述懐 第9回 脱現行受験社会(2019.5.19(Sun.))
 旧「鍛地頭-たんじとう-」の教育論〔リメイク版〕
旧「鍛地頭-たんじとう-」の教育論〔リメイク版〕 「優しさ」と「思いやり」との違い―療育的な視点もふまえて―
 ランキング(当塾比)
ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.5.12〕
 「鍛地頭-tanjito-」の国語教育論
「鍛地頭-tanjito-」の国語教育論