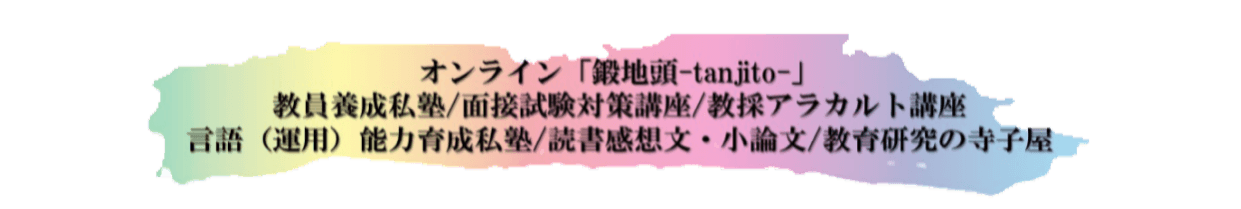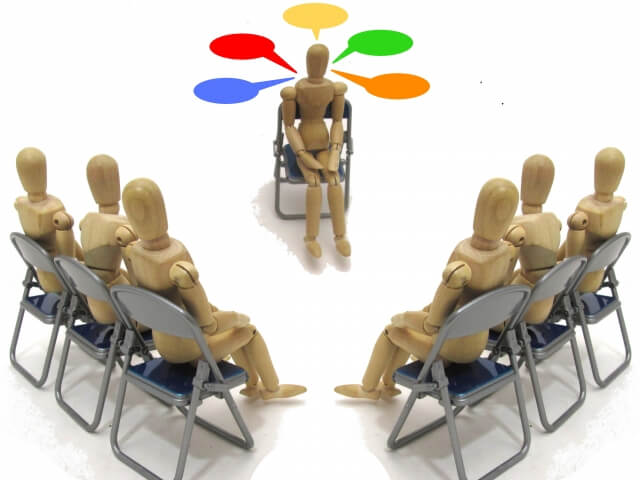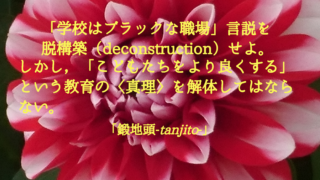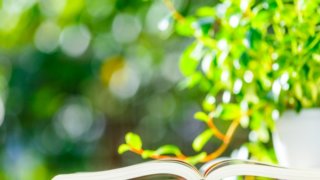0 テーマ
線形的な思考は怪我の基!!
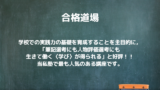

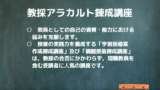

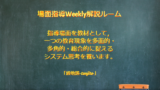
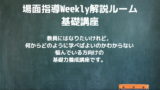
「場面指導Weekly解説ルーム」は今すぐにでもお申し込みいただけます。
「教採アラカルト基本講座」のお申し込み期間は,原則として,
令和3(2021)年2月2日(火)から令和3(2021)年3月30日(火)まで
ですが,今すぐ受講したいとおっしゃる方は,次のフォームからお問い合わせください。
お申し込み・お問い合わせフォーム

1 プロローグ
今回も引き続き,当道場にお寄せいただいたご質問に回答させていただきます。
A 問題集や参考書そのものを嫌っているのではありません。それらの使い方を問題にしているのです。
資料 「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」(平成27年12月21日)
【参考】
「教員に求められる資質能力等について(近年の提言等より抜粋) 資料4-1」(中央教育審議会 初等中等教育分科会 教員養成部会,p.4),太字及び下線等を含め,筆者が本ブログ教材用に整理しています。
最初の■がどのような資質・能力を求めているかお解りですか? その解答を当道場なりに,一部のみを披歴しましょう。
「自律的に学ぶ姿勢」は「主体的な学び」を希求します。即ちそれは〈相対化能力〉(≒文部科学省は「メタ認知」と表現している。)を必要とします。〈相対化能力〉を養うには「視点取得(perspective-taking)」が必須の条件です。多視点の形成,つまり豊かな〈相対化能力〉は「時代の変化や自らのキャリアステージに応じて求められる」(職能成長上の発達)課題を見出しやすくすることでしょう。
また一方で,「視点」の取得により「見方・考え方」が豊かになってくれば,その取得そのものへの喜びが学び続ける意欲を喚起する原動力となります。前二者の相乗効果は広義の「学力」[1]学校教育法第30条第2項に規定される学力のこと。を形成していきます。
学習指導要領で「情報活用能力」は「言語能力」等と同様に「学習の基盤となる資質・能力」であると述べられています。その育成を図るために,教科等の特質(本質)を生かした教科等横断的な教育課程が編成されなければなりません。それは多視点の形成を目的としているとも考えられます。
また同時に,認知プロセスをも鍛錬することだと思われます。新しい知識(情報・言語)の獲得は認知プロセスの初期段階に位置付く知覚(力)を育成します。それは新しい知識と既存の知識との統合を意味しています。そこでは「知識を有機的に結びつけ構造化する力」が求められるのです。[2]参考:『知覚力を磨く――絵画を観察するように世界を見る技法』(神田房枝,ダイヤモンド社,電子版,2020.10)
個々人の周辺において,また世界的規模において私たちの身の周りに生起する問題は複雑化・難化・多様化しています。これらの問題を解決するには,知覚力を鍛え,思考・判断し,その結果を実行(表現)する力(問題解決能力・コミュニケーション能力等)が求められます。……
どうですか? 略述ですが,引用文中の最初の■は上述した力量形成(一部)を言外に表現している,……そのように考えるのです。そして,これらは「これからの時代の教員に求められる資質能力」の一部に過ぎません。
筆者は塾生や受講生に最近よく語ります。
「問題解決能力が育っていない教員がどうやって児童生徒に問題解決能力を身に付けさせることができるの?」
問題集の問題を解いて,簡単な解説を読み,只管正解と解説を丸覚えする。こうした対策(当道場ではこうした在り方を「学習」とは呼ばない。)が上述したような教員に求められる資質・能力を養うのか否か,考えるまでもありません。
だから,当道場は述べるのです。
「教員採用候補者選考の準備段階から教員の研修は始まっている。」(by 「鍛地頭-tanjito-」)
「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」の〈真理〉を其方退にし,自らの合格だけを願う受験主体に多視点は形成されていません。自らにベクトルを向けた,内化した「してん」だけはたんまりとあるのでしょうが。――だからエゴイズムだと申し上げるのです。――どう見ても,どう考えてもそうした受験主体に「これからの時代の教員に求められる資質能力」が内在しているとは思えません。
多視点の形成は乳幼児・児童・生徒を多角的・多面的に理解する能力につながるのです。ここを弁えるべきです。
このように考えるならば,多視点の形成を目指す受験主体は対策の在り方を模索するはずです。問題集や参考書の使い方一つでも工夫するはずです。
では,どのように使うのが良いのか?
それについては,今後,当道場でそれをご披露する場を設定しようか否か,目下検討しているところです。
因みに,当道場の塾生や受講生には「鍛地頭-tanjito-」流の問題集や参考書の使い方で正答率を上げられた方々がいらっしゃいます。
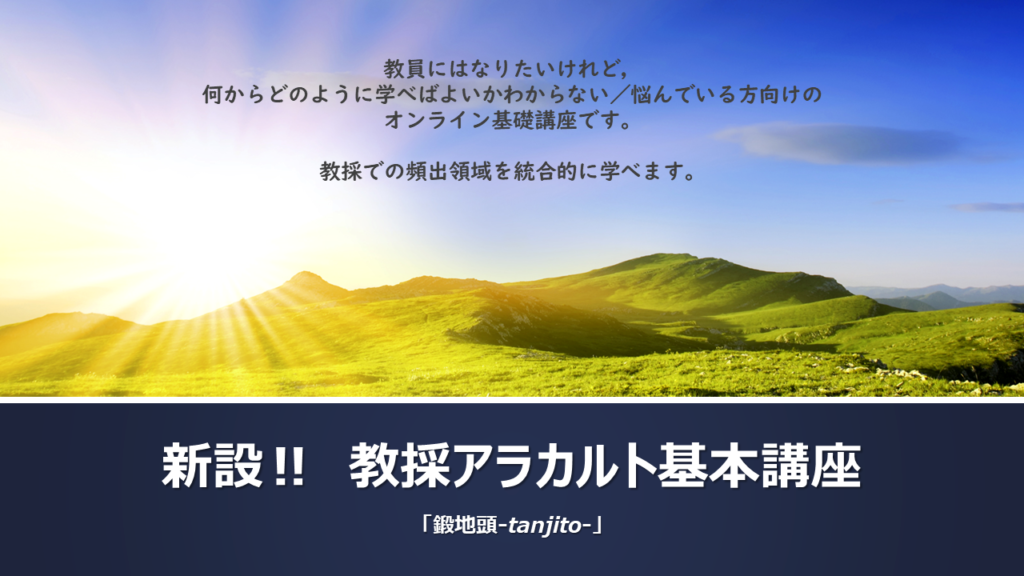
2 教採アラカルト(特別支援教育4)
(1) 出 題
問 次の文章の是非を問う。
LD,AD/HD,高機能自閉症など神経発達症を持つ児童生徒が2次障害を引き起こしてはいけないので,各自が持つ特性を自覚させてはならない。
参考: 「小・中学校におけるLD(学習障害),ADHD(注意欠陥/多動性障害),高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」(文部科学省,平成16年1月)の「第5部 保護者・本人用」の 「○本人用」
(2) ミニ解説・塾長の述懐
塾長の述懐
非常に重要な出題だと思います。神経発達症のある児童生徒の個の〈尊厳(dignity)〉にかかわる問題だと思います。
経験則に物を言わせます。飽くまでも私の職歴から来る経験談です。
神経発達症のある児童生徒を腫れ物に触るように対応される先生方がおられます。得てしてそういう方々は神経発達症のある児童生徒が問題行動を起こそうとしても/しても「いけないことはいけない。」と言えない傾向にあります。
神経発達症のある児童生徒の周囲にいる大人たち全員がそのような状況になれば,誰が「いけないことはいけない。」と教えるのですか? そうしたこどもたちは「いけないこと」が解らないまま大人になっていくのですか?
医療関係者を初めとする関係諸機関等と連携しながら,一人ひとりの特性を教職員集団で多面的・多角的・総合的に理解することを前提として,「人に危害が及ぶような危険なこと,絶対にしてはいけないこと」[3]『生徒指導提要』(文部科学省,平成22年3月,デジタル版:p.171,冊子版:p.161)に対しては「いけないことはいけない。」と指導し,できていることに対しては適時に認めることが大切なのです。
指導したことを定着させ、確実に身に付けさせていくためには、失敗を指摘して修正させるという対応ではなく、成功により成就感や達成感が得られる経験を積むこと、そしてそれを認めてくれる望ましい人間関係が周囲にあることが重要になります。
『生徒指導提要』(文部科学省,平成22年3月,デジタル版:p.171/冊子版:p.161)
「いけないことはいけない。」と指導せず,只管褒めてさえおけばそれで良いといった,腫れ物に触るような対応が上記引用中の「望ましい人間関係」とは思えません。
資料 重要
『生徒指導提要』(文部科学省,平成22年3月)の次の箇所を必ず読んでおくこと。
第6章 生徒指導の進め方,Ⅱ 個別の課題を抱える児童生徒への指導,第2節 発達に関する課題と対応,デジタル版:pp.170-174/冊子版:pp.160-163
ミニ解説
さて,本問に係る「特性の自覚」について考えるに及び,まずは教育公務員として文部科学省の資料に当たることが定石です。数種の参考資料がインターネット上にあります。検索してお読みになられることをお勧めします。
「教採アラカルト基本講座」の受講者用ブログ教材です。
パスワードが掛かっています。
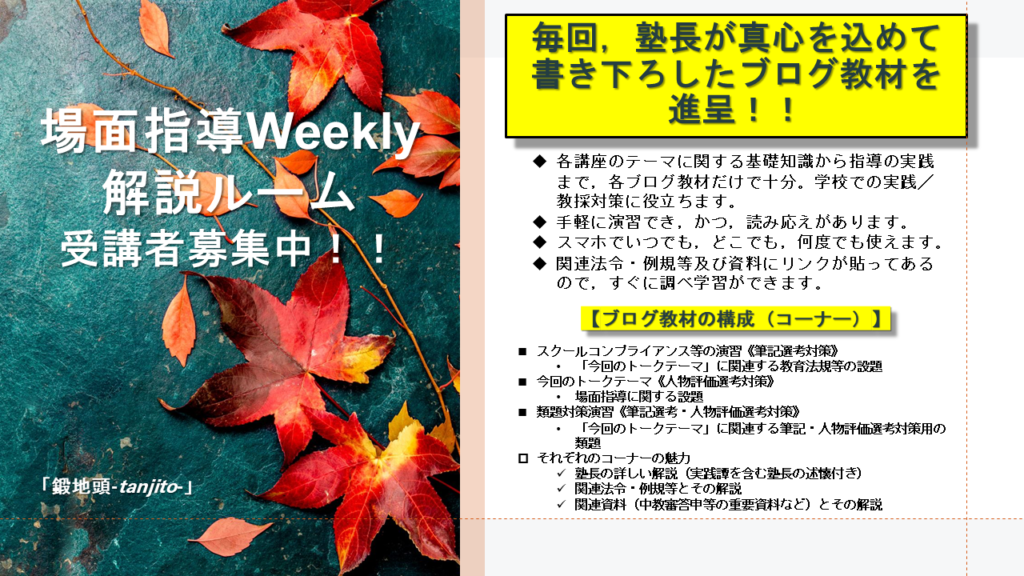
3 場面指導等(特番 面接選考)
(1) 出 題
問 いじめの問題について,(教員となる)あなたはどのように考えますか?
(2) 塾長の述懐
「どこに行かれるのですか?」
「ちょっとそこまで?」
「買い物ですか?」
「いいえ,実は膝を悪くしまして。病院です。」
「気を付けて行ってらっしゃい。」
「ありがとうございます。」
う~ん,老け込みたくはないのだが,思い付いた「会話のキャッチボール」の例がこれだった。まだ若いつもりなのだが…。年を取りたくない。
おっと,そんなことはどうでもいい。
本問は(面接選考での)所謂てっぱんネタ。てっぱんネタになることによって,受験主体が醸成する「いじめの問題」が持つ言説が空洞化・形骸化した言説に変容しないことを切に願う。
さて,仮に本問が面接選考での質問であったとしよう。皆さんは先述の膝を悪くした会話のように「キャッチボール式」で回答されるのだろうか? まさかねえ…。
キャッチボールには当然相手が必要だ。そりゃあ,コンクリートの壁でも「相手」と言えば「相手」だが,特に受験主体の場合は「面接官」の意。
本問を「キャッチボール式」で回答したならば,「面接官」はどのように思うのだろうか?
抑々,こうした出題の内容を「キャッチボール式」で回答できるのか?
「面接選考で自らの回答を冗漫に語るのは……,それは良くない。そのようによく参考書等に書いてある。会話の「キャッチボール」をしろとかなんとか。/でも,これまでの筆者の述懐は「キャッチボール式」がいけないように聞こえる…。=では,どのように回答すれば良いと言うのだ?」
「だから言わんこっちゃない。日頃から多視点を形成する訓練をしなさいと言うのです。」
「えっ,正解は? 教えてくれないの? ケチな道場だなあ!」
「あなた,「プロローグ」をお読みになられました? あなたのために直ぐには教えないのです。〈ホンモノの教員〉になるためにも,まずはご自身でお考えください。」
「えっ,その後は…。」
「ダメだこりゃあ。」
© 2020 「鍛地頭-tanjito-」
References