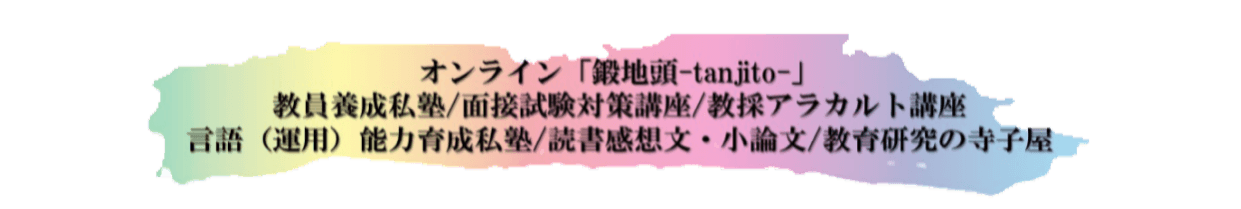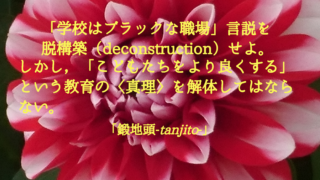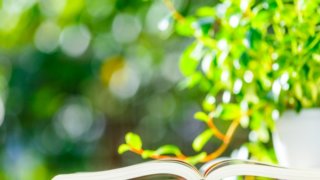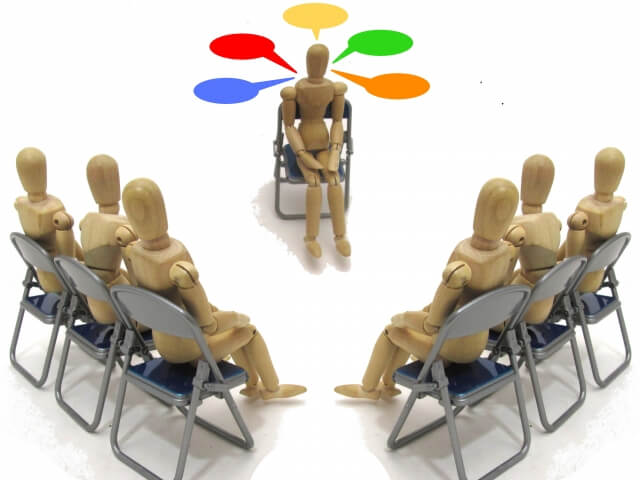0 テーマ
〈全体図〉を捉えよ!!
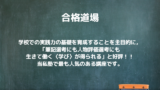

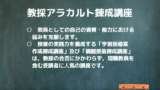

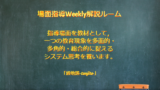
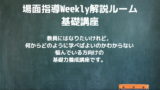
1 プロローグ
執拗ですが,今回も当道場にお寄せいただいたご質問にお答えいたします。
A システム上全てではありません。しかし,受講者の心意気次第で全てになります。
入念な調べ学習や添削指導などがシステム上ある講座は中級以上の講座(合格道場(上級)/面接試験対策講座/アラカルト錬成講座/教育研究の寺小屋(以上 中級))です[1]ただし,定員があります。少人数指導。。
しかし,入門(オープンチャット教員採用試験対策講座),基本(教採アラカルト基本講座)及び初級(場面指導Weekly解説ルーム’20)講座にはシステム上それはありません。
入門~初級講座をもう少しだけ掻い摘んでご説明します。
- オープンチャット教員採用試験対策講座(入門):元来,当道場が提示する課題に対して,ルームのルールを遵守し,建設的な「対話」を行っていただく場として設置したものです。現在,機能化できていないことがとても残念です。
- 教採アラカルト基本講座(基本):本ブログ教材シリーズの「2 教採アラカルト」のコーナーで採り上げる出題を中心に塾長が解説を加えます。その解説はインターネット上では発信しない教育に関する理論と長年の実績に基づく実践とをマッチアップした内容です。だからこそ,教員採用候補者選考(以下,「教採」と表記)対策のポイントをズバリと指摘します。学校現場で必要・重要な事柄が教採で問われるのですから,理論と実践との統合的な解説は必然的に教採のツボを押さえることになるのです。したがって,当初から「ここが教採のポイント!」と大上段に振り翳す解説等は,その統合的な解説になり得ないわけで,学校現場で〈生きて働く知識〉にならないのです。逆は真ならず。同じ解説を聴くならば,一挙両徳が宜しいかと。しかも,本講座では受講者用のブログ教材(非公開)が別に用意してあります。さらに,受講者層に合わせ,指導のレベル・方法等を自由自在に変えていきます。
- 場面指導Weekly解説ルーム’20(初級):本ブログ教材シリーズの「3 場面指導等」のコーナーで採り上げる出題を中心に塾長が解説を加えます。学校現場で生起する教育事象は複雑な要素が三次元的に絡み合う有機的な多面体です。したがって,その教育事象を扱うことは,学校教育に関する数多の知識・技能を習得し,かつ,それらを対象に合わせて統合することを学ぶことにつながります。実践で生かすことのできる知識・技能,思考力・判断力・表現力等の基礎を身に付けることができるのですから,講座の回数を重ねるたびに実践的意欲が芽生え,わくわくしてきます。これが次の学びへと継続する原動力となります。ここでも非公開のブログ教材を用意しています。一教材10,000~18,000字程度の強烈な教材(教採のポイント,中教審等の必読資料及び塾長の実践談並びに筆記試験対策練習問題等で構成)で,この教材だけで他の参考書は不要のはずです。教採アラカルト基本講座同様,受講者層に合わせ,指導のレベル・方法等を自由自在に変えていきます。

講座の設定(システム)上,調べ学習や添削課題がないだけで,受講者が自ら調べ,考えるなどして講座に臨めば,教育効果は倍増します。要はホンキで真面な教員になりたいか否かの問題です。
A それはご自身の問題です。
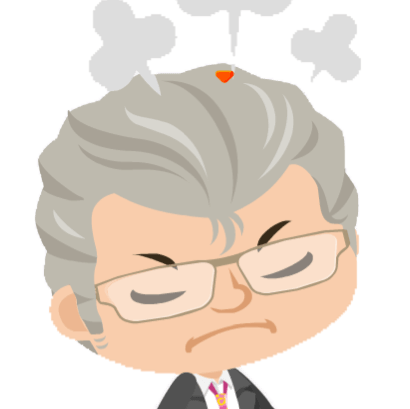
また「合格だけしたい」言説か!?
何か他に事情があるのかもしれないが…。
そうであるならば,ご相談いただきたい。
当道場の基本理念は「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」。そのために,その基本理念を常に持ち続け,責任をもって教育活動に勤しむ教員となるため,とことん,徹底的に「鍛地頭(=総合的な人間力を鍛えるの意。)」することを目的としている道場が「鍛地頭-tanjito-」なのです。教員研修の実施主体として長年その身を置いてきた塾長が熟練の技で鍛え上げるのです。
したがって,過去に数多の教員を見てきた塾長が塾生や受講者に向かって「あなたは合格までに3年を必要とするよ。」などと申し上げることだってあるのです。資質・能力が合格のレベルに達していない方々が数多くいらっしゃる中で,端から「当道場で学ばれたら,来夏,一発合格です。」などと騙るような無責任なことは致しません! 塾生や受講者の資質・能力を見抜くことには,当然,自信があります。何はともあれ,そのような出まかせの言葉はご当人のためにならない。いつも申し上げているように,当道場はビジネスライクに運営しているわけではないのです。
当道場の教えに忠実に,どれだけホンキで修業を積まれるか。ただ,それだけです。だから,最後の船着き場である当道場に出会われ,15年目にして合格された方々が現実にいらっしゃるわけです。ご本人のやる気次第。その意欲を燃やすお手伝いをさせていただくのが「鍛地頭-tanjito-」です。
だからこそ,中級以上の講座ではお一人おひとりの資質・能力を見極めながら,かつ,お一人おひとりとご相談しながら,各自に適合する課題を一問ずつ手づくりし,指導内容,指導方法,レベル,進度等を個に合わせ,日々,鍛錬していただいているのです。「オーダーメイド型教採家庭教師」と呼んでくださる方々がいらっしゃるのは,その所以です。

〈ホンモノの教員〉を一人でも多く各都道府県等の学校に輩出したいんだ!
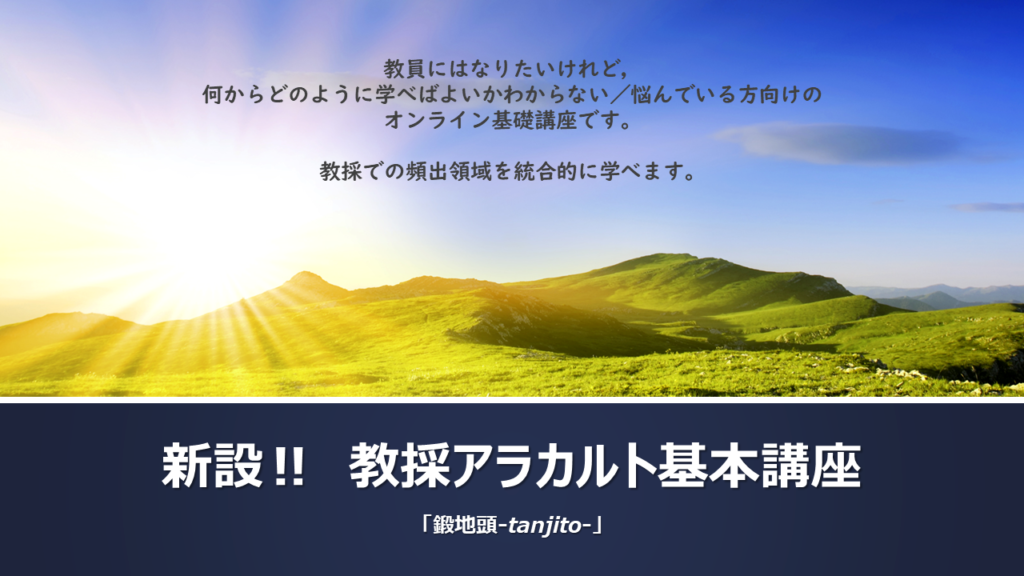
2 教採アラカルト(特別支援教育3)
(1) 出 題
問 『特別支援学校 幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領』(文部科学省,平成29年4月)には,「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」についての2つの記述がある。両者の違いについて簡潔に説明しなさい。
(2) ミニ解説・塾長の述懐
ミニ解説
まずは,各自で教育公務員として用いなければならない典拠を求め,観点を明確にした上で,「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」との相違を見出すこと。「相違を明確にする」とは共通性にも思考の裾野を広げてみるということです。
例えば,「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」との目的における共通点・相違点は何ですか?
「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」との共通点・相違点が解れば,両者の連関性を捉えることができます。それは何ですか?
塾長の述懐
学校というところは往々にして「つくること」が目的化する傾向にあります。「個別の指導計画」にしても,「個別の教育支援計画」にしても然り。つくり終えたら業務終了というわけです。これでは教員の文章作成能力はちょっぴり上がっても,ほぼ何も役に立たない。
令和元(2019)年11月27日(水),「教員採用試験対策講座「鍛地頭-tanjito-」」のトークルームで筆者は次のように発言しています。
ただ,「個別の指導計画」とは何か,「個別の教育支援計画」とどう異なるのか,両者をどのように作成するのか,作成した後,どのように活用するのかなど,「個別の指導計画」・「個別の教育支援計画」だけを話題にしても,まだ具体化して(お話して)おかなければならないことがあるのです。
註:( )は引用時に挿入しました。
「「両者の違いについて簡潔に説明しなさい。」と言うのだから「違いについて簡潔に説明し」ました。」――全くもって指示待ち人間,正解至上主義型人間,問題集一辺倒型人間。〈新しい時代〉の〈新しい教育〉を担う教員の資質・能力には欠けた人たちです。管理職としては欲しくないタイプ。失礼! 私情を交えてしまいました。…A
本問を見て,少なくとも「両者をどのように作成するのか」,「「個別の指導計画」の作成から実際の指導のつながりについては如何様に考えるべきか」,「作成した後,どのように活用するのか」など考えられて,教採の受験主体としてはまあ普通の資質・能力の保有者だと思うのです。…B
実際,学校で指導に当たる教員には,例えば,当該児童生徒の正しい特性の理解力及び問題の抽出力,その問題を解決する能力及び指導力,関係諸機関を含む校内/外の連携能力(協働性,コミュニケーション能力,文章作成能力等),当該教育活動に係る評価能力(メタ認知力)などが一般的に必要とされる資質・能力なのです。…C
A,B,Cの格差や如何に。
「初任者や教職経験の少ない者にそんな資質・能力を一挙に求められるわけがないだろうが!」
「そうですね。が,しかし,そういう言述が束ねられることにより醸成される,また意識裡でも,無意識裡でも,醸成させようとする言説の権威性がどれだけ乳幼児・児童・生徒を愚弄するものかお解りですか? それで教員だと言えますか!」
「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」です。
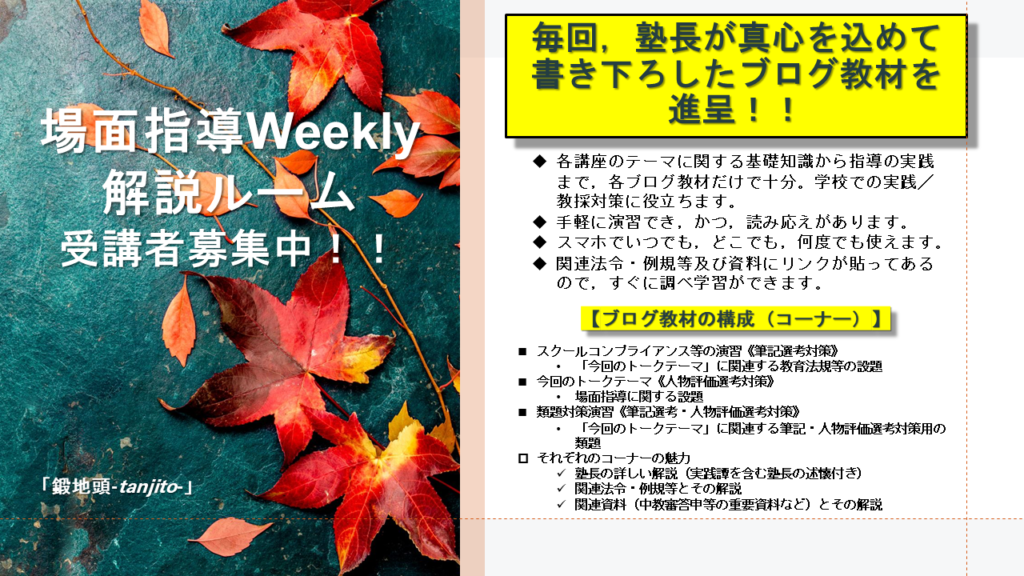
3 場面指導等
(1) 出 題
問 保護者から担任のあなたに入電しました。電話の内容は,「先程,息子が帰宅しましたが,担任の先生に叩かれたと言って激しく泣いています。先生,どういうことですか!?」というものでした。保護者はやや興奮気味です。
この後,あなたはどのように対応しますか?
(2) 塾長の述懐
本問をお読みになって脳裡に「何」が浮かびましたか? 条件反射として〈何〉に対して「ナニ」を真っ先に形象化できたか? それが教員としての資質・能力の多寡を分けるのだと思います。この〈何〉が最も大切なのです。だから,それを教育の〈不易〉と呼ぶのだと思います。したがって,国の,将又,各地方公共団体の「求める教師像」にそれはあるわけです。教採で見られる資質・能力です。
本問をお読みになって,いくつの「対応」(のポイント)を瞬時に思い浮かべられましたか?
「3つですか?」
「全く足りません。それでは「対応(指導)」できません。恐らく,そうした思考は線形性(linear)によるものだと思います。」
「5つですか?」
「それでも足りません。「対応(指導)」できないか,却って保護者等とトラブルを起こす確率が高いと思われます。」
「10以上ですか?」
「それならば,何とか「対応(指導)」できると思います。勿論,10の内実が肝心ですけど。」
たとえば,全体が部分aと部分bからできているものを考えよう。部分aの性質がkであると理解され,部分bの性質もkであると理解されたとき,(a+b)の性質もkであると理解してもよいかどうか。そう理解してもよいというのが線形的(linear)な思考である。
『小論文を学ぶ―知の構築のために―』(長尾達也,山川出版社,2001年8月,p.74)
多角的,多面的,総合的な視点をもって,できる限り,教育事象(例えば,本問のようなケース)をありのままに捉える(システム思考の)訓練をしてください。一つの教育事象を分解し,しかも寡少な視点で部分部分を組み合わせても,全体(一つの教育事象)を再構築できません。
場面指導の出題は,それを意識してか否かは分かりませんが,必然的にそれを求めることになっているのです。学校現場での「対応(指導)」はそうしたレベルですよ。
「では,どうやってそれらの「視点」を身に付けろというのか!?」
「まあ,問題集の問題だけを解いていてもほぼ実を挙げることはできないでしょうね。でも,解かないより解いた方が良い。最も良いのは深い教育実践を行ってきた人に訊くことでしょうかね? 場面指導の出題が現実に教育現場で生起する教育事象をテクストとして切り取って構成されているのだから,実践的な「視点」の多くは現実の教育実践に内在していると述べるより他はないわけです。問題集の解答・解説がそうした「視点」を全く形成しないとは言いませんが,教育実践に内在する「視点」は量的にも質的にもそれらを遥かに超えているのです。日常の教育現場の生きたコンテクストに内在するものですから。抑々,問題集の解答・解説が形成する「視点」があったとして,それを眼前の教育事象を対象として,例えば,問題解決するのにどうやって統合するのですか? その方法が分かりますか?
深い実践経験と実践的な理論が十分でない方々にそれを求めるのは酷な話です。それなのに,場面指導の出題は増加傾向にある。それだけ学校現場が逼迫しているということですよ。〈ホンモノの指導力〉を持つ教員が必要だということです。「即戦力・実践力」が要るのです。
だから,「鍛地頭-tanjito-」が「場面指導Weekly解説ルーム」を開設したのですよ。本問の場合,10以上の「視点」となぜその「視点」が必要なのか,そうしてそれらの「視点」を本問のコンテクストに即応させてどのように統合するのかなどを塾長が熱く〈語る〉のです。そうすれば,問題集や参考書のレベルから得る知見は自ずと習得されていきます。問題を解いて正答率が上がるのは当たり前の話です。
教育事象の中心は言うまでもなく「乳幼児・児童・生徒」です。これは偽らざる事実です。「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」はそういう意味でもあるのです。大きな「視点」をそこに当てない限り,周縁部の小さな「視点」は見えてきませんよ。即ち,教育事象の全体図をありのままに捉えられないのです。
© 2020 「鍛地頭-tanjito-」
References