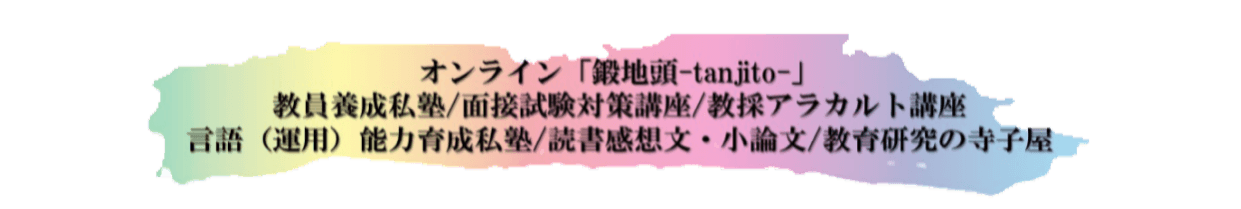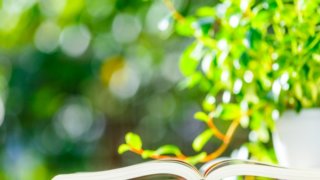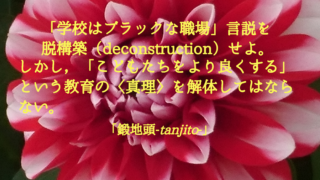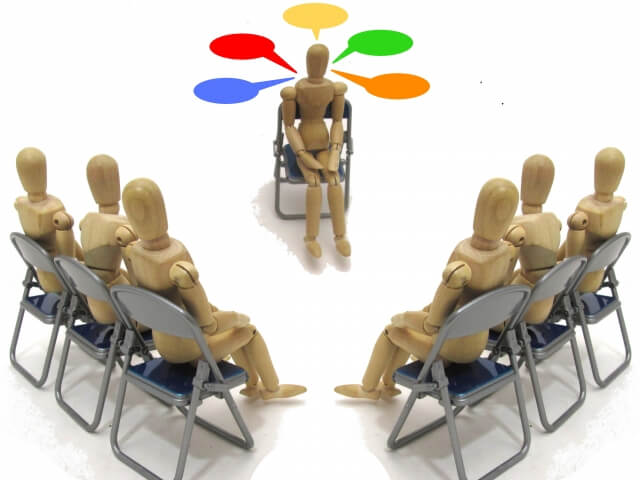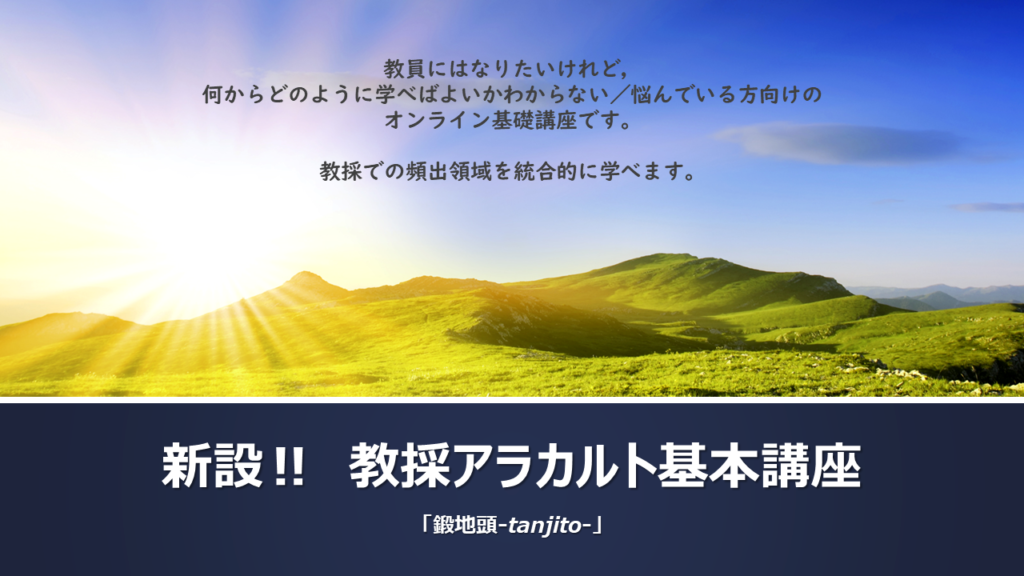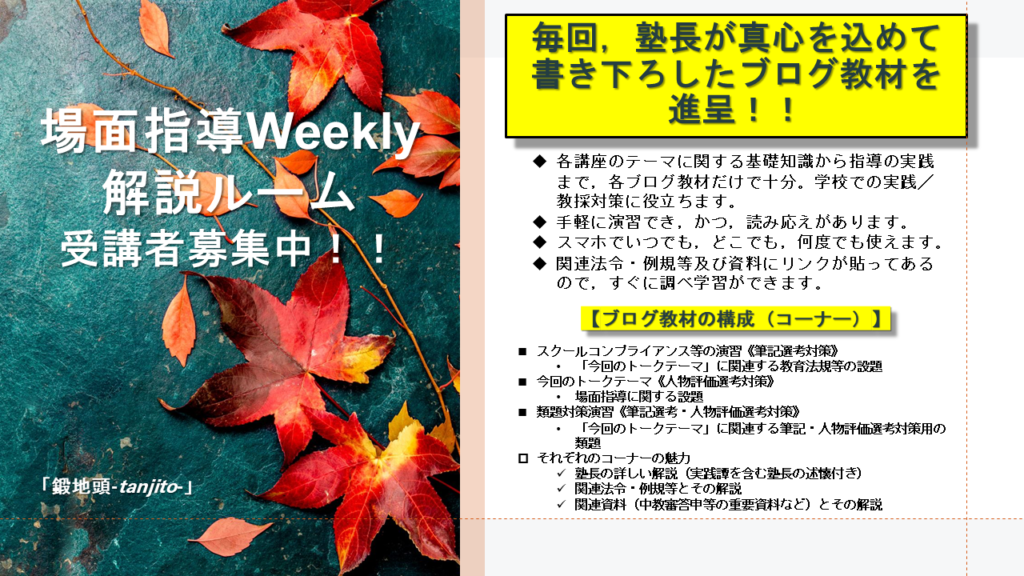0 テーマ
教員の資質能力―「恕」と〈教育愛〉―
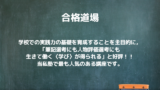

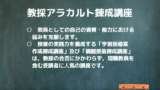

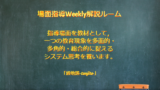
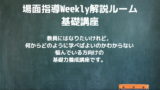
「場面指導Weekly解説ルーム」は今すぐにでもお申し込みいただけます。
「教採アラカルト基本講座」のお申し込み期間は,原則として,
令和3(2021)年2月2日(火)から令和3(2021)年3月30日(火)まで
ですが,今すぐ受講したいとおっしゃる方は,次のフォームからお問い合わせください。
お申し込み・お問い合わせフォーム

1 プロローグ
別にここでぺダンティックに弄するつもりはない。また,道場内で恒常的に言葉の遊戯を楽しんでいるわけでもない。これは紛れもない事実であり,「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」との熱き〈教育愛〉が紡ぎ出すSpecial Team内でのあるメンバー(F先生)とのチャットによる「対話」[1]令和3(2021)年1月4日 午前1時4分である[2]本ブログへの掲載に際して,F先生のご承諾がある。。
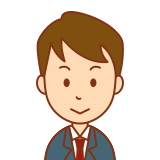
こんばんは。
夜分失礼します。
本日,『第三項理論が拓く文学研究/文学教育』[3]『21世紀に生きる読者を育てる 第三項理論が拓く文学研究/文学教育』(田中実・須貝千里・難波博孝編著,明治図書,2018.10)を読み,感動が冷めやらないので,思わずメッセージを書いている次第です。
私は高校の授業を行わないので,実践のページは読まず,
「総論 第三項理論が拓く文学研究/文学教育」[4]前掲書pp.245-283の章を読んでおりました。
277ページ[5]前掲書,Ⅱ 文学教材による教育の目的とその姿を読んだ時,
2019年7月21日から9月まで小桝先生にコンサルティングしていただき,得た境地そのものであると感じました。
とすると,第三項理論に基づいた授業方法は,学習者と教師が一問一答で行う授業や,教師が一人でしゃべりまくる講義式の授業はありえないことになります。また,学習者が一人で行う学習も,自己に閉じこもる可能性が高く,ここでは取り上げないことになります。一方で,学習者同士がただグループを組んで行う授業もありえないことになります。なぜなら,ただグループを組んで行うだけでは,学習者自身や他の学習者の解釈/読みを疑い続けるような契機が生まれないからです。
前掲書,Ⅱ 文学教材による教育の目的とその姿,p.277
私の中で「パラダイムシフトが起きた」と当時,浅はかな自身の言説がありましたが,
この読みの構造は,国語の物語・小説にかぎったことではなく,
言葉による見方・考え方そのものであると私は考えました。
言葉が概念より後にできたか,先にできたかの話も「総論」では掲載されておりました。
池田晶子氏の言説[6]前掲書において前文について池田明子氏の論を踏まえながら解説してある。です。
ともあれ,第三項の存在を鑑みながら,モノを見ていく。
ポスト構造主義の予測不能な時代に入っていくからこそ[7]F先生のお考え。当道場では現代はポスト構造主義の終焉期にあると考えている。,どんな構造が現代を包んでいるのか,その時代を生きるために,内なる声をどれだけ研ぎ澄ませることができるか。
だからこそ,学ばなければならないと認識しました。
小学校現場で第三項理論を生かした実践ができるか。
総論にはかんたんな実践例のモデルが掲載されておりました。
学びの多い本を紹介していただき,ありがとうございました。

F先生,こんばんは!
やはり時代は一元論の時代へ向かっているのだと思います。
現代は二元論から一元論への丁度マージナルな位置付けにあるからこそ,宇宙の意思による禊を受けている。
そんな気がします。
宇宙の意思は言語理論を超越したところにあります。
〈人為〉を《相対化》するとき,言語を超えた《声》が聞こえるのだと思います。
それはまるで野に咲く一輪の花がそよ風に揺蕩うようです。
小桝のコンサルティングの話題がある。当道場の面接試験対策講座の中で嘗てものしたF先生との〈対話〉のことだ。了解・到達不能の「ありのままの《自己(他者)》」を希求する《旅》を指す。「主体的,対話的で深い学び」の「対話」はそうした〈対話〉でなければならない。
F先生は前掲書との〈対話〉の中で,ご自身の言語観を揺さぶられている。書物なる「他者」との「対話」を経由した自己の内なる他者との〈対話〉は,自らの言語観を〈相対化〉する〈旅〉の始まりであった。そこには学習指導要領が求める〈学び〉の相貌(資質能力の三つの柱,主体的,対話的で深い学び)の一面が垣間見える。
そして,そこには主体的に学び続ける教員の姿がある。溢れんばかりの〈学び〉の感動をありのままに体感・表出する,〈学び〉に誠実なお姿に学び続ける教員としての資質能力を見る。
絵空事を物語るのではない。
現代・次世代を生き抜く乳幼児・児童・生徒たちや教員を含めた大人たちの課題を鑑みるとき,まずは他者を媒介に〈自己の内なるボイス〉を傾聴しなければならないだろう。そうした行為の日常的な反復は「恕」[8]当道場では他者を思いやり,自己を思いやる意として用いている。を生起せしめ,やがて身辺をそよそよと吹き抜ける一過性の時代の微風にさえ,単身耳を欹てることになるだろう。教員としてそれを支えるものは熱き〈教育愛〉である。
2 教採アラカルト(教員の資質能力vol.2)
(1) 出 題
問 次の文章は「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について~学び合い,高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて~(答申)」(中央教育審議会,平成27年12月21日)の「3.教員の養成・採用・研修に関する課題」の一節である。空欄A~Iを適語で補いなさい。
◆ 豊かな知識や識見,幅広い( A[9]視野 )を持ち個性豊かでたくましい人材や特定の教科や指導法についてより高い( B[10]専門性 )を持った人材を教員として確保する必要がある。
◆ 多様で多面的な選考方法を促進するため,各教育委員会が実施する( C[11]採用選考試験 )への支援方策が必要である。
◆ 教員の採用に当たって,学校内における( D[12]年齢構成 )の均衡に配慮し検討することが必要である。
時代の変化に伴い,教員を目指す人材が変化している中,従来,優秀な教員を確保するため,都道府県教育委員会等は,( E[13]求める教員像 )を明確かつ具体的に示し,当該教員像に合致する者の採用に適した選考方法の工夫を行うべきことが提言されてきた。今後は後述する教員の( F[14]育成指標 )を作成し,それを踏まえるなどの取組を進めていくことが必要である。
また,学校に対するニーズが複雑化・多様化する中,豊かな知識や識見はもとより,幅広い( A[15]視野 )を持ち個性豊かでたくましい人材を教員として確保することが必要である。また,一層多様化している児童生徒の( G[16]興味・関心 )に対応するため,特定の教科や指導法の一部についてより高い( B[17]専門性 )を持った人材の確保も重要である。
都道府県教育委員会等は,これまでも( H[18]人物 )を重視した採用選考を実施しており,真に教員としての( I[19]適格性 )を有する人材の確保に努めているところであるが,中には( C[20]採用選考試験 )の作成が大きな負担になっているとの声も聞かれるところであり,多様で多面的な選考方法を促進するためにも,各教育委員会が実施する( C[21]採用選考試験 )への支援方策が必要ではないかとの指摘がある。
さらに,大量退職・大量採用の影響などにより,地域や学校によっては,30代,40代の教員の数が極端に少なく,学校内における( D[22]年齢構成 )の不均衡が生じている。( D[23]年齢構成 )の均衡がある程度取れた状態の方が組織として望ましいとの指摘もあり,各任命権者における教員の採用に当たって,これらのことについても検討することが必要である。
(2) ミニ解説・塾長の述懐・資料
ミニ解説 塾長の述懐
「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について~学び合い,高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて~(答申)」(中央教育審議会,平成27年12月21日)の「3.教員の養成・採用・研修に関する課題」,「(2) 教員採用に関する課題」,p.15からの出題です。
出題のねらいは現在の教員採用候補者選考(以下「教採」と表記)が置かれた状況(現状と課題)とこれからの新しい時代の新しい教育を担う教員としての資質能力を理解するとともに,各受験主体の立ち位置を明確化することにあります。
なお,こうした現状と課題を受け,同答申の「4.改革の具体的な方向性」,「(2) 教員採用に関する改革の具体的な方向性」,p.29(一部抜粋)には,次のようにあります。
資料
◆ 国及び各都道府県の教育委員会等は,後述する( A[24]教員育成協議会(仮称) )における協議等を踏まえ,採用前の円滑な入職や最低限の( B[25]実践力 )獲得のための取組を普及・推進する。
◆ 国は,教員採用試験の( C[26]共通問題 )の作成について,各都道府県の採用選考の内容分析やニーズの把握等,必要な検討に着手する。
◆ 国は,後述のように( D[27]特別免許状 )授与の手続の改善を図るなど活用を促進する。
◆ 国は,( D[28]特別免許状 )以外にも,教員免許を有しない有為な外部人材を教員として確保するための方策について検討する。
教員採用に関しては,後述の( E[29]教員育成指標 )を踏まえつつ求める教員像を明確にした上で,男女共同参画等の動きを踏まえつつ,引き続き( F[30]人物 )重視の採用を進めていくことが必要である。さらに,学校における教育課題が多様化する中,多様な( G[31]専門性 )を持つ教員を採用していくことが重要であり,( D[32]特別免許状 )の活用等による学校外の人材の採用を推進する必要がある。
また,採用の際の( H[33]ミスマッチ )の防止や新規採用者の円滑な教職の開始のため,入職の前後における研修や( I[34]学校現場体験 )の機会を設けることも重要であるとともに,( J[35]年齢構成 )の不均衡を是正するための方策を検討することも必要である。
さらに,一般に教員の採用時期が国家公務員等の採用時期と比べても遅く,( K[36]優秀な人材 )を確保する際の課題となっているとの指摘もある。就職・採用活動時期の変更の趣旨や( L[37]教育実習 )の実施時期なども踏まえつつ,改善のための検討を進めるべきである。
塾長の述懐
〈語り手〉の危機に瀕する逼迫した焦燥感が読み取れるコンテクストです。教員の資質能力の低下が叫ばれて久しい緊迫した現状を肌で感じることができるか。それも教員に必要とされる資質能力の一つでしょう。
各受験主体の自己内に〈教育愛〉はあるのか。
ここが全ての始まりです。
参考
3 場面指導等(暴力を振るう児童生徒への対応)
(1) 出 題
問 学級(ホームルーム)担任をする児童生徒の保護者複数から担任のあなたに要望がありました。
「C君はよく学級(ホームルーム)で他の友達に暴力を振るっています。授業中も立ち歩いたり,教室を飛び出したり,他の友達にちょっかいを出したり。こういう問題のあるこどもを何とかしてください。クラス替えをするとか,転校させるとか。」
あなたならば,このように発言する複数の保護者にどのように連携しますか?
(2) ミニ解説・塾長の述懐
ミニ解説
【保護者連携(対応)をテーマとする場面指導の考え方】
1 大原則として保護者連携に臨むときの教職員に必要な態度(在り方・考え方等)を考える。
2 出題された個別事案を細かな場面(ピース)に分けて考える。
※ 本問においての細かな場面に分けたそれぞれの具象及び連携(対応)等については省略。
塾長の述懐
大仰に「保護者連携(対応)をテーマとする場面指導の考え方」と題して,非常にざっくりと2点に言ってのけました。これらのポイントは何も教採だけではなく,学校現場での常套の考え方でしょう。「1」と「2」とを共時的に実行しなければならないわけです。
分析的思考ではあるのですが,学校現場でも問題となる状況を把握した際には,瞬時に対応の対象となる場面をピースに分け,そこにある課題を抽出し,抽出された課題を統合化しながら,事実全体の構造を損なわないように(ここが難しい),事案の事実を脳内でスクリーン化・ストーリー化し,かつ,並行して,解決策を構造化しながら,保護者等への言動を即座に紡ぎ出す。
まあ,これが従来の「生徒指導のプロの技」なのでしょうね。
しかし,〈ホンモノの生徒指導のプロの技〉はこうした「分析→統合」の手法は取らない。なぜならば,統合化を図っても元の完全な全体に再構築できないからです。したがって,〈ホンモノの生徒指導のプロ〉はシステム的に問題から解決策までを共時的・全体的に捉えるわけです。
実は,〈ホンモノの教員〉・〈ホンモノの生徒指導のプロ〉には,問題事案を耳にした瞬間に,「このように対応すべきだ。」という一種の閃きが必ず起こります。ただし,事実の細部を明らかにしなければならない。誤った事実に基づく判断による閃きだったらいけないですし,しかも,それは誤った指導につながるから。だから,例えば,事実を情報伝達する他者等の話を真剣に細かく聴き取るのです。
それだけ,「児童生徒をより良くするのだ。」との熱き〈教育愛〉に根差す経験や経験知を含む脳内の引き出しをたくさん持っていて,数々の問題解決の場に自ら率先して立ち,他の教職員と協働しながらドラスティックな実践を行ってきているから,問題抽出から解決策の構造化まで瞬時に,共時的・全体的にストリーミングできるのです。
デカルト二元論による分析・統合型の生徒指導は「生徒指導のプロ」のレベル,一方,システム思考による総合型の生徒指導は〈ホンモノの生徒指導のプロ〉のレベルというところでしょうか。
© 2021 「鍛地頭-tanjito-」
References