場面指導Weekly解説ルーム
受講者募集
(定員 30名)
本講座は場面指導対策として学校現場で頻発する教育事象を採り上げながら,多面的・多角的・総合的に対象を捉え(システム思考),学校現場で生きて働く指導原理・指導方法・根拠法等を教職歴29年の塾長が解説する講座です。学校教育のあらゆる角度から一教育事象を掘り下げ,理論的・実践的に考究することから,教員としての資質・能力の基礎を育成することができます。また同時に,筆記選考と人物評価選考との両者を兼ね合わせた対策を行うことが可能です。つまり,教員研修を基盤とした〈新しい時代〉の新しい教員養成講座というわけです。乳幼児・児童・生徒のために,そして,教員を目指すあなた自身のために〈ホンモノの実力〉を本講座で身に付けましょう。
講座日程・講座数
令和4(2022)年2月26日(土)から同年7月9日(土)まで
毎週土曜日
午後8時00分から午後10時00分まで
全20講座
お申込期間
令和3(2021)年11月2日(火)から同年12月28日(火)まで
1 「さくら先生日記」
塾長の述懐
塾生であるさくら先生(中学・家庭)が綴る「ブログ教材」の第二弾です。
今回は嬉しいことに,さくら先生が塾長の大学院時代からの長年の研究テーマである「「語りの構造」読み」[1] … Continue readingに挑戦してくれます。
「語りの構造」を構築する「語り手」概念は,今次,学習指導要領(中学校・高等学校 国語編)にお目見えしました。
それは主に高等学校の学習指導要領解説に語られているのですが,中学校の解説においてもわずかに触れられていることを鑑みるとき,いずれ小学校でも展開される可能性あると言えそうです。――しかし,発達段階からして,そうした〈読み〉の行為は難易度の点において困難か?――
いずれにせよ,中学校・高等学校と「語り手」概念を用いた読みの行為を学習者が習得する運びとなるならば,今後,国民全体に「「語りの構造」読み」が流布・浸透していくと予想されます。
このような時代の趨勢にあって,さくら先生が「「語りの構造」読み」に挑戦することは大変に意義のあることです。
さくら先生の前には大きな壁である〈新しい読みの行為〉が立ちはだかることになりますが,果敢に挑まれんことを期待します。
[追伸]
恐縮ながら完結しておりませんが,当私塾には「「語りの構造」読み」に関するブログ教材シリーズがあります。それらを一瞥していただいて,さくら先生のブログ教材をお読みになられると,先生が言わんとされておられることが一層理解しやすいのではないかと思います。
「「語りの構造」読み」シリーズ
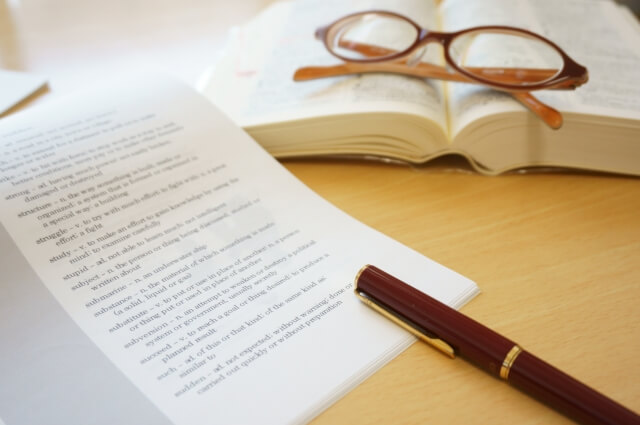
国語教育のみならず,現代の教育が児童生徒に養わなければならない能力は,大人が身に付けるべき能力でもあった。塾長が自らの修士論文において20年前に指摘した現代を生きる者の課題とその解決の一方途。それらが今次改訂の新学習指導要領及び解説(国語)に。「語りの構造読み」から展開する独自の教育論をご堪能ください。
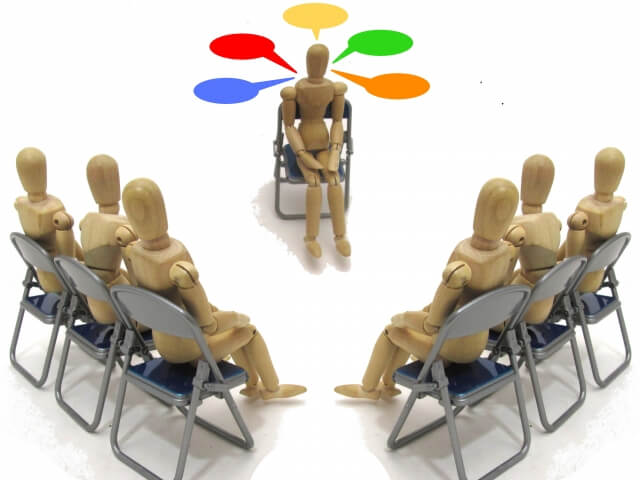


新学習指導要領(国語)に初お目見えした「語り手」概念を解説する第2弾。今回は,特に「語りの構造と語り手の視点」について概説します。しかし,本ブログシリーズの目的は国語教育の推進だけではございませんので要注意。来たるべき一元論的トランスモダンの時代を如何に《生きる》か,その壮大な究極的命題に挑むことが最たる目的なのです。
「さくら先生日記」
「まずは「語り手」を探せ!」
以前,「鍛地頭-tanjito-」1.0時代にSpecial Teamのメンバーで〈学び〉を深め合う「寺子屋ICT」という研究会がありました。[2]さくら註:現在は「鍛地頭-tanjito-」2.0時代の到来に伴う講座等の改編によって「教育研究の鍛地頭」と改称されています。その研究会の中で,私はある板書計画 (道徳)を提案しました。そして,メンバーの方々から貴重なご意見を数多く頂いたのです。
教材は「お月さまと コロ」(文部科学省作成教材,小学校1・2年生対象)でした。この教材を「語りの構造」で読み,「対比的で構造的な板書(計画)」を作成・提案しました。
こうした経験を通して,私は「語り手」を中心に作品を読むことの重要性に気付くとともに,作品世界に存在する「語り手」なる存在に興味・関心を抱くようになったのです。
以上のような 事情から,今回は,次のタイトルで綴ることにします。
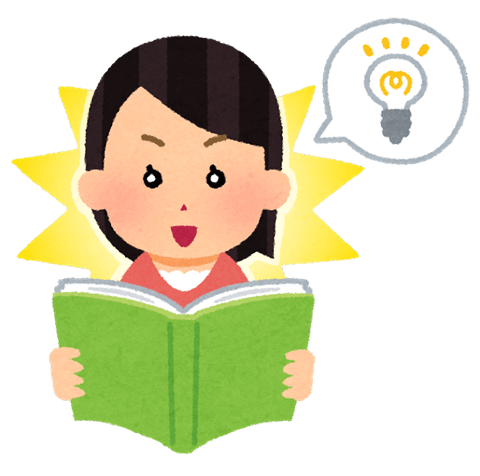
タイトル:まずは「語り手」を探せ!
私はこれまで,小説や物語を読む際に,私自身が登場人物に同化し,その心情やその変化ばかりに着眼してきました。
『わたし(私)たちの道徳』(文部科学省作成教材)を繙き,手始めに1つ教材を読んでみようと思った矢先のことでした。塾長が次のような言葉を投げ掛けてこられました。
「小説や物語だろうが,説明的な文章[3] … Continue readingだろうが,その作品世界には必ず語り手の存在があるんじゃ。歌詞,雑誌,ニュース記事など,ありとあらゆる作品世界にのう。」
その日からというもの,作品世界を訪れる私は必ず「語り手」を探そう/出会おうと心掛けるようになったのです。
「語り手」は何を意図して「読み手」に語ろうとしているのだろうか?
その「語り方」は?
塾長はこうした「語り手」の意図を「語り手の欲望」と呼んでいます。
読む行為のキーワードは「まずは「語り手」を探せ!」です。こうした行為によって,「語り手」との「対話」が「読み手」の見方・考え方をより一層広げ深めてくれるのです。
つづく
【執筆後の振り返り】
授業者として学習指導要領が何よりも大切だと学びました。
【塾長のつぶやき】
さくら先生とは数々の道徳教材(文部科学省作成)を,「語り手」の素性をできるだけ明確にし,その種々の語り方に着眼しながら,再構築しました。その上で,「語り手」の欲望に辿り着こうと腐心しましたね。「語り手」は作品世界中の架空の人物です。いろいろな人がいたことに驚かれたことでしょう。ですが,実は,この「種々」や「いろいろな」が「語り手の欲望」に到達するためのポイントとなるのです。もうそのことに気付かれていますかね…?
『高等学校学習指導要領解説 国語編』に言表「語り手」が19か所表出していると教えてくださったのはさくら先生でした。同解説に「語り手」概念が語られていることは早くから承知していましたが,「19か所」とは気づきませんでした。さすがいつも精緻に調べ学習をされるさくら先生です。
その「19か所」を意識されながらお読みになられたご感想が「授業者として学習指導要領が何よりも大切だと学びました。」ですね。何はともあれ,教育公務員です。まずは,ここからスタートです。当私塾の捉える「語り手」概念とは多少異なってはいますけれど(笑)
2 近頃の「鍛地頭-tanjito-」
現役時代,生徒から付けられたあだ名は「ノストラコマス」だ。
「(生徒名)よ~,そろそろ気持ちを落ち着かせておかないと,2週間後に(当該生徒による問題行動によって)特別な指導を受けるようになると思うで。落ち着けよ。」
授業中,半身で板書しながら,敢えて当該生徒から視線を切り,低いドスの効いた声で予言する。[4]普段から生徒たちとの人間関係をつくっているからできるのだ。
2週間後,当該生徒が問題行動を起こしそうになるくらいアレている。[5]その間,全職員で当該生徒への指導を継続している。
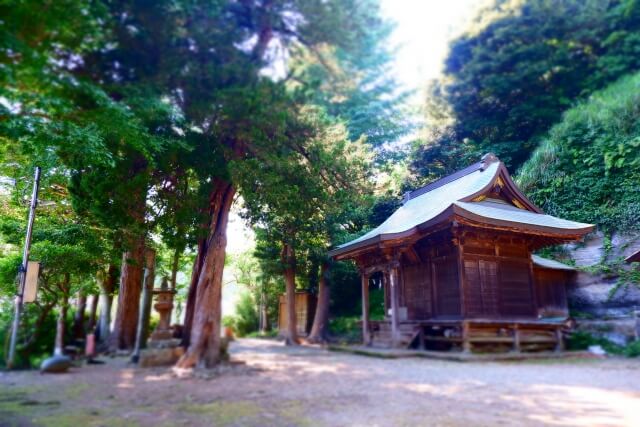
「参ったのう💦 なんで,先生,ここにおるん?」
元気でやんちゃな生徒たちがタイマンを張る舞台に先回りして鎮座。それを阻止・指導する。
こうしたことがよくあった。
しかし,その予言力も齢とともにひ弱になった。ある予言を覆すことが起きたのである。
「塾生の皆さんからブログ教材用の原稿を募集します!」
(皆さんは非常にご多忙だ。そんなに簡単に名乗りは上がらないだろう。)
その予言は3日と保たなかった。甘かった。
(このままだとSpecial Teamのメンバー全員から応募がある! 添削[6]Special Teamのメンバーの場合,無料だ💦のため,寝られんようになるでぇ💦)
確定稿の嚆矢となったのがさくら先生の「育児日記」第一弾(タイトル:あな)である。塾内は俄かに活気付いた。
「塾生の方々が力を付けてくだされば,寄稿が殺到してもそれで良い。嬉しい悲鳴だ!」
この場合,
「まずは,塾生ありき」
なのか…,
塾生は口々に語る。
「このまま教壇に立つのでは心許ない。」
「自らに(学)力を付けたい。」
「教採に合格してから教壇に立つまでの期間の過ごし方が肝心だ。」
………
だから,教採に合格した後も当私塾に残り,Special Team内の研究(部)会や各種講座で塾生たちは学び続ける。
当私塾において合格/不合格の垣根は存在しない。合格した者もこれから合格する者も同じ「鍛地頭-tanjito-」(「個別」と「協働」の〈学び〉の空間)で学ぶのだ。
なぜこうしたことが成就するのか。
当私塾のメンバーは常に眼前にいる/いることになるであろう児童生徒を見つめている。だから,みんなで頑張れるのだ。
「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」の信念の下に。
3 ポッドキャスト
塾生が塾長を評するに,「👹のような」が頻繁に翳される。塾長を知る人は学問や職務に対しては〈厳しい〉ことを了解している。妥協しない。猪突猛進する。しかし,それは塾長の信念である。塾長の場合,学問や職務は「乳幼児・児童・生徒」の存在があって成り立っている。「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」 だから〈厳しい〉。「👹のような」と翳される。だからこそ,塾生や読者を初めとする皆様に伺いたい。「厳しさ」の定義を。教採の選考項目である「論作文・小論文」のテーマにも「厳しい指導」がある。
4 塾長の述懐ー「多様な価値観(価値の多様性)」の〈相対化〉ー
「D&I」
昨今,よく耳目に飛び込んでくる。「D」とは「ダイバーシティ(簡潔に述べれば「多様性」の意)」,「I」とは「インクルージョン(「包含」・「包摂」の意。「インクルージョン教育」は,英語では「inclusive education」である。)」である。
特に,「ダイバーシティ」について言及すれば,経済産業省には「ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライン 」(平成29年3月(平成30年6月改訂))がある。「多様性の時代」を象徴している。
「多様性の時代」を象徴すると言えば,その最たる言表は「多様な価値観(価値の多様性)」ではないだろうか。巷間でも,学校教育界でも当たり前のように用いられ,最早空気のような存在と化した。
ホントウの「自由な市民社会」を目指すに当たって,「多様な価値観(価値の多様性)」を相互承認し得ない状況はあり得ないだろう。しかし,「最早空気のような存在と化した」現況には憂苦するのである。アトム化した群衆が「多様な価値観(価値の多様性)」に醸成する〈ぼうりょく〉的な言説を〈相対化〉する機を逸してはならない。
このように言述すると,筆者は〈ぼうりょく〉が付帯する相対主義的全体主義者のように思われるかもしれない。だが,それは違う。
「多様な価値観(価値の多様性)」はテレビ番組「水戸黄門」で多用されるご老公様の印籠ではない。
ところが,現代,アトム化した群衆の数多くは個々の懐に「たようなかちかん(かちのたようせい))」という名の印籠を忍ばせ,自らにとって都合の良いコンテクスト上でそれを振り翳し乱用する。――例えば,自己内への他者の温かい来訪をその印籠で食い止め,自らはその印籠を他者の面前に押し付け,臆面もなく他者の内部へと不法侵入する(「たようなかちかん(かちのたようせい))」言説によって生じる現代社会の力学)。――寄らば大樹の陰。アトム化しているからこそ,大樹「たようなかちかん(かちのたようせい))」の言説下に参集するのである。したがって,寄り集まった群衆間に他者意識に根付く,人としての〈つながり〉はない。そこはエゴセントリズムの巣窟である。
同様の既に社会現象と化した事態が学校社会でも生起していないか? 教職員間のいじめや職員室カーストなどはその典型的な表象である。
エゴセントリズムの土俵上でアトム化した我利我利亡者たちが「たようなかちかん(かちのたようせい))」を個別に挙って連呼し続け,そこにある種の拡散的統一性を有する〈権威〉が宿れば,「たようなかちかん(かちのたようせい))」は「絶対的な価値観(価値の絶対性)」と化し,〈普遍的な認識〉を持とうとする〈小さな価値観〉を〈ぼうりょく〉的に蹂躙する。
抑々,「多様な価値観(価値の多様性)」の地平には間主観的拘束性による「共通了解(認識)」があって,初めて相対的に「多様な価値観(価値の多様性)」が相互承認されるのではないだろうか。
仮にそうであるならば,その地平を超越する〈普遍的な認識〉に辿り着こうとする意思こそ,ホントウの「自由な市民社会」を希求する〈自由〉ではないのか。
こうして考えてみると,既述した現代のアポリアは大衆のアトム化による原子的存在としての個の孤独感・不安に起因しているように思えてならない。それは教職員集団の現状と言えるアトム化と二重写しになる。だからこそ,教職員間のいじめや職員室カーストは維持される。
そうした悪辣で輪廻するエゴイスティックな環境から自己を解放するには,〈普遍的な認識〉の形成過程を理解し,ホントウの「自由な市民社会」の〈普遍的な認識〉を求める意思と実践意欲を養うことしかない。
では,学校教育界における〈普遍的な認識〉とは?
それは紛いもない「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」の精神なのである。これしかない。
「また,それか!」と思われるとして,そう思われるあなたが教職員,もしくはそれを目指される方であるならば,現状の学校の「ふへんてきなにんしき」に収斂されると思われている「たようなかちかん(かちのたようせい))」を一々〈相対化〉してみられると良い。相対主義者ならば,何も残らないのであろうが,そうでないならば,残るものはただ一つだけである。
「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」
〈ホンモノの教員〉はそのような〈相対化能力〉を鍛えている。しかも,学校教育界を含む部分社会や各種領域,そして社会全体のフレームを常に脳裡の片隅で〈相対化〉しながら教育活動を営んでいる。
(完)
5 「論作文・小論文」選考・問題を〈相対化〉する―いじめの問題―
問 あなたはいじめの問題にどのように対応していきますか?
論作文・小論文の「つれづれ〈相対化〉シリーズ」。相も変わらず,今回も心に移り行くよしなしごとをそこはかとなく綴ることにする。
問いに対して,方法論だけに思考が向くようならば,教員には向いていない。いじめの問題には立ち向かえない。いじめの問題はそんなに軽いものではない。こどもたちの命が懸かっているんだぞ。選考の在り方を見直すべきだ。
いじめの問題への対応には〈正解(普遍的な認識)〉があって,それは一つしかない。どうしても選考項目としての「論作文・小論文」で本問を問うならば,その一点のみを評価すれば十分だ。方法は自ずと付いてくる。抑々教育活動とはそういうものだ。
こうした問い(の連続)がいじめの問題を形骸化していく。形だけの似非-教員をつくる。だから,こうした問いそのものを〈相対化〉できる〈ホンモノの教員〉を育成すべきであるし,教採はそのような資質・能力を有する者を選別すべきである。
古い資料であるが,次の資料を紹介しておく。古い資料であっても,いじめの問題への取組みに係る考え方は,今も変わらない。特に「【参考】2 指導の進め方と留意点」は学校が組織的な対応を行う際の考え方・手順として非常に有意義である。参考にしていただきたい。
【参考資料】
「生徒指導資料№28(改訂版) いじめの問題への取組みの徹底のために」(広島県教育委員会,平成18年12月)
児童虐待の問題にしてもそうだが,こどもたちの命の懸った/懸るいじめの問題を教採対策として表層の知識だけを並べ立て言述することは誤りである。表層の知識だけを覚えて,それらを繋ぎ合わせ,選考項目の「論作文・小論文」とする前に,学ぶべきことがあるのだ。教採自体が知識の羅列のみを評価しているとすれば,いじめは跋扈してもなくならない。このような理由から,今回は本問についてこれ以上語ることはしない。職務上,いくつものいじめの問題と必死で向き合ってきた人間の本音である。
© 2021 「鍛地頭-tanjito-」
References
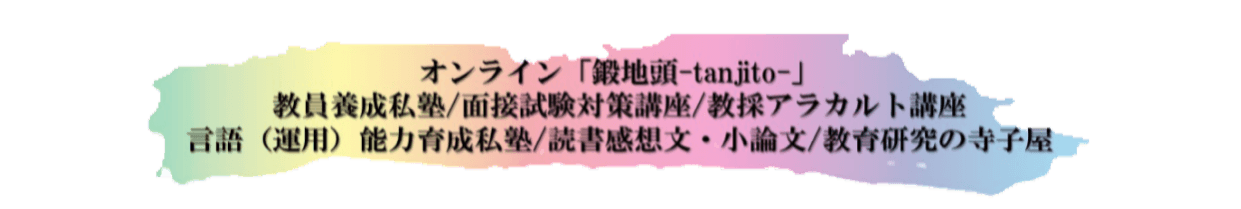










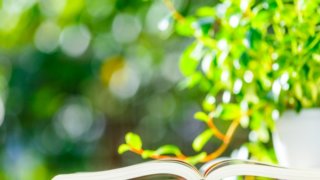

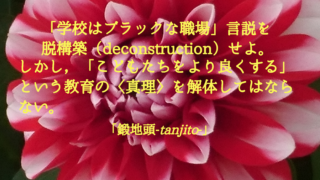








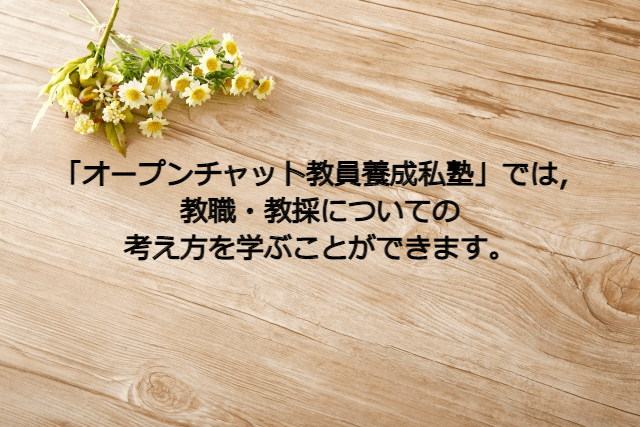
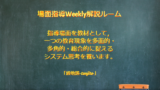
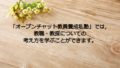

塾長註:訳があって,敢えてざっくりとした問いのリード文とした。