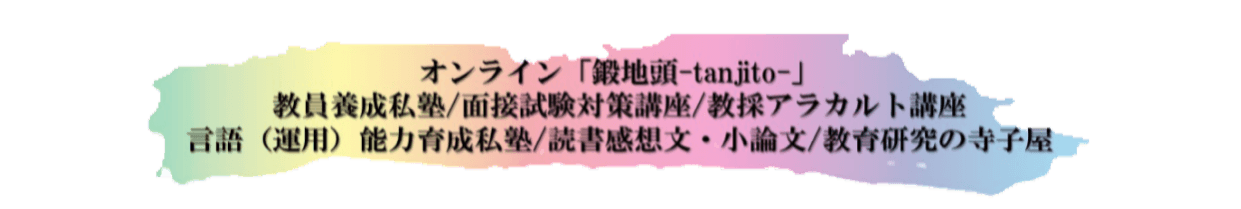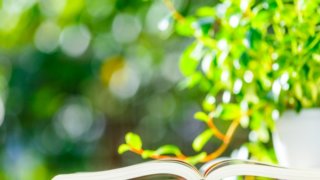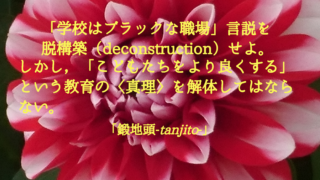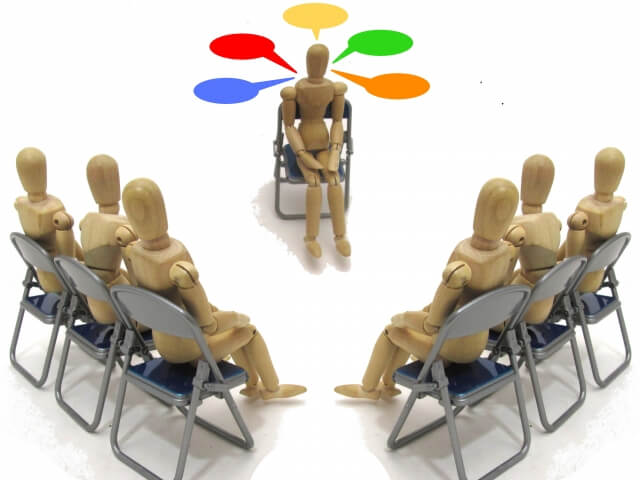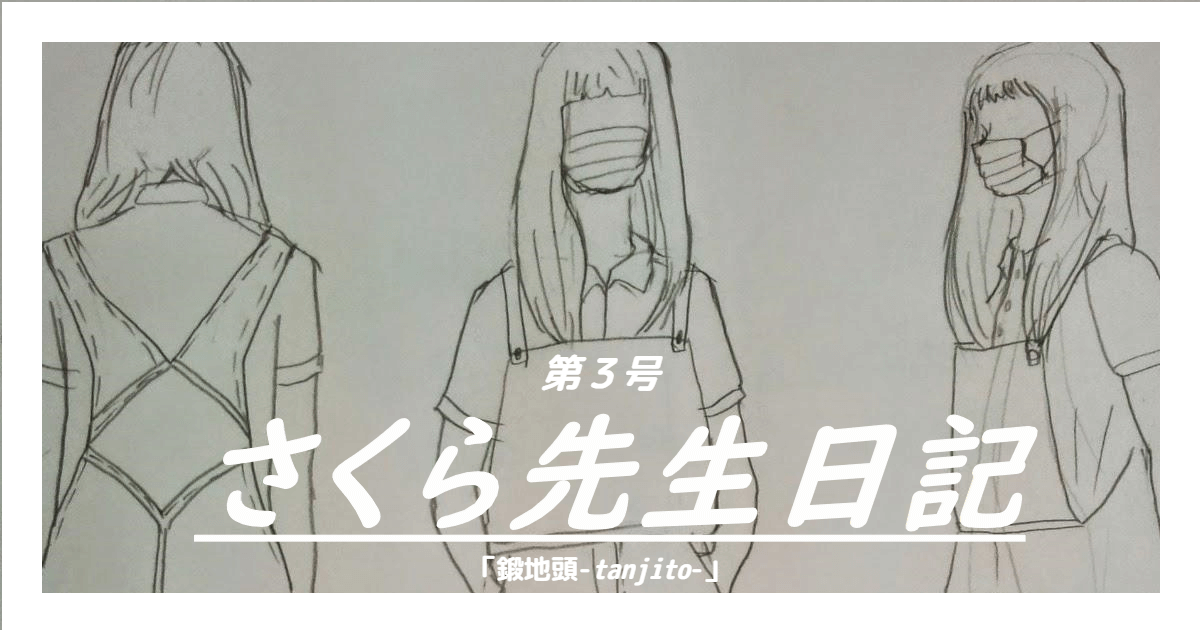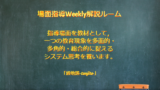場面指導Weekly解説ルーム
受講者募集
(定員 30名)
本講座は場面指導対策として学校現場で頻発する教育事象を採り上げながら,多面的・多角的・総合的に対象を捉え(システム思考),学校現場で生きて働く指導原理・指導方法・根拠法等を教職歴29年の塾長が解説する講座です。学校教育のあらゆる角度から一教育事象を掘り下げ,理論的・実践的に考究することから,教員としての資質・能力の基礎を育成することができます。また同時に,筆記選考と人物評価選考との両者を兼ね合わせた対策を行います。つまり,教員研修を基盤とした〈新しい時代〉の新しい教員養成講座というわけです。乳幼児・児童・生徒のために,そして,教員を目指すあなた自身のために〈ホンモノの実力〉を本講座で身に付けましょう。
講座日程・講座数
令和4(2022)年2月26日(土)から同年7月9日(土)まで
毎週土曜日
午後8時00分から午後10時00分まで
全20講座
お申込期間
令和3(2021)年11月2日(火)から同年12月28日(火)まで
「さくら先生日記」
「おいしい」
「目指せ,300字!」第9弾,今回は「育児日記」シリーズからです。
Cちゃん:ちょーだい!? おにく!!
私 :野菜もちゃんと食べようよ。
Cちゃん:野菜,いなない(いらない)。
私 :え~…にんじんは? トマトは?
Cちゃん:いなない。にんじん,いなない。トマト…いなない。
ここ何週間もCちゃんは野菜を避けて食べています。(肉食系女子なのでしょうか💦)
子ども特有の一時的な好き嫌いだと良いのですが。以前はちゃんと食べていました。
実はここのところ,Cちゃんと私と2人だけの朝食・昼食・夕食だったのです。
Cちゃん:パパ,しごちゅ(仕事中)。
特に夕食時,パパの席を見つめながら,少し寂しげにつぶやいていたのです。そのような日々が続いたのです。
そして,一昨日,パパが久しぶりに早く帰宅し,夕食に同席したのでした。
Cちゃん:かんぱい,しよっか!
お茶が入ったコップを持って嬉しそうに自ら盃をかかげ,号令を発します。
しかも…
Cちゃん:おいしい!! おいしいねぇ!!
ちゃんと野菜を食べています。
みんなで食べると“おいしい”のでしょう。
「共食」の大切さをCちゃんに教えられました。
夕食が終わった後も,Cちゃんは何度も繰り返していたのです。
「おいしかったねぇ。」
つづく
【執筆後の振り返り】
まずは,教職を志す者こそ,「共食」の大切さを忘れるべからず。
みんなで一緒に食卓を囲んで、共に食べることを「共食(きょうしょく)」と言います。共食には、一緒に食べることだけではなく、「何を作ろうか」と話し合って一緒に料理を作ったり、食事の後に「おいしかったね」と語り合ったりすることも含まれます。
「「食べる力」=「生きる力」を育む 食育 実践の環(わ)を広げよう」(内閣府大臣官房政府広報室,政府広報オンライン,「暮らしに役立つ情報」,3.食べることの「楽しみ」って?)
【塾長のつぶやき】
一読後,何やら熱いものが胸中に沸き上がった感じがしました。それは私だけでしょうか?
Cちゃんは,お母さん(=さくら先生)が受講されている当私塾のリモート講座の終わりに,必ずディスプレイに顔を出して来て,しゃかりきに手を振ってくれます。
バィバイ。バィバイ。
さくら先生と出会って,約600日が経過しますが,まだ歩いていなかった頃のCちゃんにお目に掛った時から,「しっかりしたお子さんだ。」と思っていました。
そして,私もCちゃんに教えられたのです。
「共食」の大切さは既に以前から声高に言われています。上掲の定義(内閣府)を併せ,私自らの人生経験と照らし合わせても,「共食」は大切だと思います。「孤食」が当たり前となる昨今の風潮(ライフスタイル)を考え合わせると,余計にも「共食」の大切さを痛感します。
だって,形態上は「きょうしょく」でも「孤食」の「きょうしょく」が蔓延しているのですから。
外出先のファミリーレストラン等でも日常の光景となりました。家庭で食卓を囲む時もそうなのでしょう。食事中,幼いこどもたちがしきりに保護者と視線を合わせようとする。しかし,保護者はそれに気づこうが,気づくまいが,自らのスマホの画面に無言で視線を落とし,夢中になる。それは,決して食事時だけではありません。
(保護者に)無視される。気持ちを受け止めてもらえない。
特にこどもが幼少期にそういった光景の中で過ごすならば,間違いなく愛着(アタッチメント)の形成が歪みます。「心の安全基地(Secure Base)」を持たないこどもたち。そうしたこどもたちはやがてどうなるのか…。
Cちゃんは私に〈ホンモノの共食〉を教えてくれたのです。
それにしても……,
「まずは,教職を志す者こそ,「共食」の大切さを忘れるべからず。」
「教職(きょうしょく)」と「共食(きょうしょく)」…まさかさくら先生はオヤジギャグをおかましになったのでは…💦…ないと思うのです。この最後のフレーズ,噛み締めれば,噛み締めるほど意味深長ですね。
【資料編】
さくら先生の強っての希望があって(笑),上掲のブログ(「おいしい」)をお読みいただく上で,参考にしていただきたい法的な根拠等を引用しておきます。(塾長)
(子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割)
食育基本法(平成十七年法律第六十三号) 施行日: 平成二十八年四月一日 (平成二十七年法律第六十六号による改正),e-GOV,法令検索
第五条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。
また、家庭での共食は食育の原点であり、食を楽しみ、家族とのつながりを大切にする食育を推進していくことが重要である。家族との共食については、全ての世代において、家族とコミュニケーションを図る機会の1つである等、重要と考えられている一方で、若い世代における実際の共食の頻度は少ない傾向にあり、若い世代を含む 20~50歳代では、仕事の忙しさが困難な要因の一つとなっている。
農林水産省,第4次食育推進基本計画,第3 食育の総合的な促進に関する事項,1.家庭における食育の推進 ,(1)現状と今後の方向性
次の資料も参考にしてください。
(学校給食の目標)
学校給食法 昭和二十九年法律第百六十号,e-GOV,法令検索
第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。
一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。
衣服の歴史(ババシャツ編)
「目指せ,300字!」第8弾,今回は「THE 家庭科」シリーズから。
木枯らしが吹き始め,秋を飛び越して冬が到来したような風情です。寒さ対策から重ね着を始めました。
そんなとき,ふと想起した言葉があります。
「ババシャツ」
最近では「ババシャツ」という言葉を聞かなくなったように思います。ちょっと前まで,「ババシャツ」は中高年の女性が着る物といったイメージがありました。
しかし,現代,幅広い世代が「インナー」を着用してます。それは「ババシャツ」が進化したものです。
衣服は私たちの日常生活に欠かせないものでありながら,当たり前のものであり,普段何気なく身に纏っています。
昔の衣服と現代の衣服とを見比べ,素材や衣服の呼び方,形の変化に着眼点を置けば,現代が急速に発展を遂げたことに気付くのではないでしょうか。
「衣服」と「言葉」と「時代の変遷」。
何気ない日常生活に「衣服」の歴史を垣間見たのです。
つづく
【執筆後の振り返り】
衣生活を取り巻く課題を多面的・多角的・総合的に考える。
衣生活を取り巻く課題については,科学技術の発展により変化する被服,繊維産業のグローバル化,衣生活と被服を取り巻く現状を様々な角度から理解できるようにする。
『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 家庭科編』(文部科学省,第1部 各学科に共通する教科「家庭」,第2章 家庭科の各科目,第2節 家庭総合,2 内容とその取扱い,B 衣食住の生活の科学と文化,(㆓) 衣生活の科学と文化,ア(ア ) 衣生活を取り巻く課題,日本と世界の衣文化など,被服と人との関わりについて理解を深めること,平成30年7月,p.68)
日本と世界の衣文化については,気候や風土に応じ,また,人々の生活習慣や宗教,様々な規範に基づき,歴史的に発展してきた背景等を理解して関心をもつことができるようにする。
被服と人との関わりについては,なぜ人は服を着るのか,その動機や衣文化の変遷などから関心をもち,既製服の生産と流通について理解し,循環型社会の持続に配慮した衣生活,健康・快適・安全な被服の在り方について理解を深めることができるようにする。
また,古くから伝わる年中行事や地域の催し物等を通して,和服の意義と役割を理解し,我が国の衣文化の継承・創造を担う一員として自覚できるようにする。
塾長のつぶやき
「当たり前」を〈当たり前〉として〈相対化(≒メタ認知)〉できる能力が,現代を生きる我々には必要なのだと思います。そして,特に教職員には必要であり,それが教職員としての大切な資質・能力の一つだと思うのです。
さくら先生から「衣服の歴史(ババシャツ編)」の初稿が手元に届いた際,初見で感じたことがありました。
こうした視点で文章を書けるのは,さくら先生の鋭敏な感性があるからであり,教科の本質である「見方・考え方」とご本人とが日常的に一体化しているからである,と。
また,当私塾で当私塾流の「学習指導要領の変遷史」を学んだからか…と。
「時代の変遷」とともに,求められる「学力(観)」も変遷します。「学力(観)」が変われば,例えば,教育方法も変わってくる。教育システムも変わるわけです。
これら三者の連関性を的確に理解し,今,そして,これから教職員が何を行っていかなければならないのかと模索する。
これが学習指導要領の変遷を学ぶ意義であり,「歴史に学ぶ」ということなのです。
そして,その連関性に二項対立(二律背反)をトランスした〈教育の不易流行〉を見る。
これが〈ホンモノの教職員〉の一様相です。
「衣服(学力)」と「言葉(教育方法等)」と「時代の変遷」…なのです。
© 2021 「鍛地頭-tanjito-」