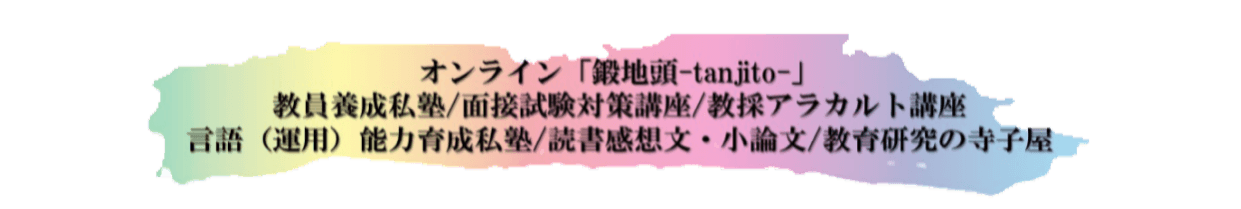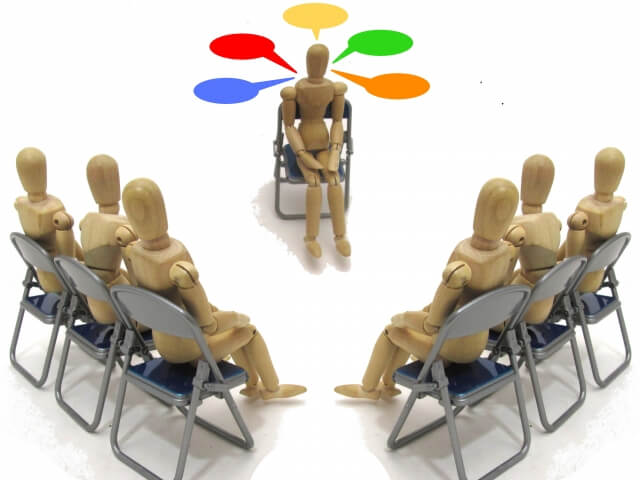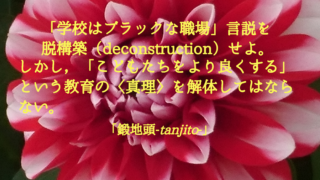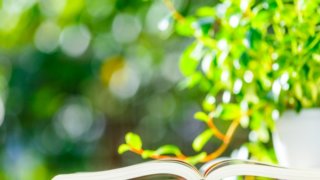0 テーマ
今こそ,
「乳幼児・児童・生徒―社会―学校」等のつながりを
〈相対化〉せよ!!
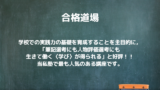

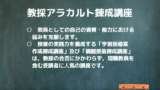

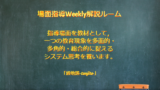
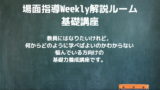
1 プロローグ
前回のブログ教材でお知らせしたように,当面,本「プロローグ」において,当道場へお寄せいただいた,共通する内容を有する質問にお答えしていきたいと考えます。
Q ブログ教材でなぜ具体的な解答・解説を行わないのですか?
A 申し上げたいことは大別して2点あります。
- 無料受講者等(読み手)の学力を付けたいから。
- 解答・解説の内容を盗用する方々がいるから。
質問には「当道場の各種講座に誘導したいと考えているのだろう?」といったメタメッセージがあるように思います。(解答・解説の)続きを聴きたいと思わせて各種講座に誘導する手口……そのような手垢の付いたやり方で稼ごうなど邪で卑しい気持ちは毛頭ありません。「では,手垢が付いていない手口ならばやるのか?」……やりません。当道場が我が身を削って個別指導や講座等を行っていることは,塾生や受講者がよくご存知です。
「1」について。本ブログ教材等をお読みくださる方々の多くは教員志望だと思います。そうであるならば,学習指導要領が求めている学力観は重々ご承知のはずです。また,なぜそのような学力観が措定されているのか,その歴史的・時代的背景,経緯もご存知のはずです。
そうした方々に「○○が教員採用候補者選考(以下,「教採」と表記)によく出題されるから,この答えと解説を○○のように覚えておきなさい。」という旧態依然とした,ある意味,誤りと言える教採対策法を勧めること自体がおかしいのです。そのようなことをして,無料受講者等の「学力」が付くわけがない。
しかも,当道場の講座では「学力(資質・能力)の三要素」について重ねがさね角度を変えながら解説に熱弁を奮っています。――熱弁を振るわなければならない根拠もあるのですが,「2」の理由によりここでは述べません。――さらに,児童生徒にそうした「学力」を身に付けさせる教育課程・教育方法等について論じ,当該「学力」を有した塾生・受講生がその教育方法等を教壇で実践できることを目途に指導を継続しているのです。教員志望者が身に付けなければならない「学力」は明らかなのです。
にもかかわらず,教採に合格だけすれば良いからと,正解主義一辺倒の指導では,そうした「学力」は養えません。このような「学力」を有しない教員志望者を教壇に立たせるわけにはいかない。それが「鍛地頭-tanjito-」です。
困るのは「学力」を有しない教員に教わる「(乳幼児・)児童・生徒」です。
空欄補充や選択肢問題等だけがまるでゲームのように上手にできるようになった。このような対策ばかり行っていると,自然とそうした方法が身に付き,そうした方法でしか学習者に教えることができなくなります。
困るのは「学力」を有しない教員に教わる「(乳幼児・)児童・生徒」です。
だから,ブログ教材上の出題に対して自ら調べ,自らの頭で考える癖を付けて欲しいのです。
「2」について。由々しき,かつ,忌々しき問題です。当道場の顧問弁護士と相談しながら何度も警告を発しているのに,当道場のブログ及びブログ教材等の内容及び表現を盗用し自らの稼ぎにされておられる複数の団体があります。
そうした方々に金銭を稼がれるのが嫌だという気持ちは二の次です。
学校での指導というものは同じ指導でも対象となる個々の児童・生徒及び状況等に応じて微妙に異なったニュアンスを帯びます。しかし,その微妙さが指導の対象となる(乳幼児・)児童・生徒には大きな影響を及ぼします。
教採をビジネスライクに考えておられる方々の中には学校での指導経験が皆無,もしくは,寡少な方々がおられ,それでいながら「指導者」を名乗られた上に,例えば,場面指導の出題に対する解説を騙られている現状があります。しかも,その内容が当道場の〈語り〉の盗用であるとき,微妙で繊細なニュアンスは抜け落ちてしまいます。中には,成文化されていない地方自治体(教育委員会等)の指導を無視した〈騙り〉が展開される場合もあると伺います。
その〈騙り〉を信じ込んだ受験主体が本務者となった暁に,その〈騙り〉に即した指導を継続して行ってしまう。どうなると思います?
困るのはそうした教員の指導を受ける「(乳幼児・)児童・生徒」です。
生兵法は大怪我の基。このとき「大怪我」をするのは(乳幼児・)児童・生徒です。
したがって,当道場は道場内において,塾長が自らの言葉で〈語る〉に尽きると考えているのです。
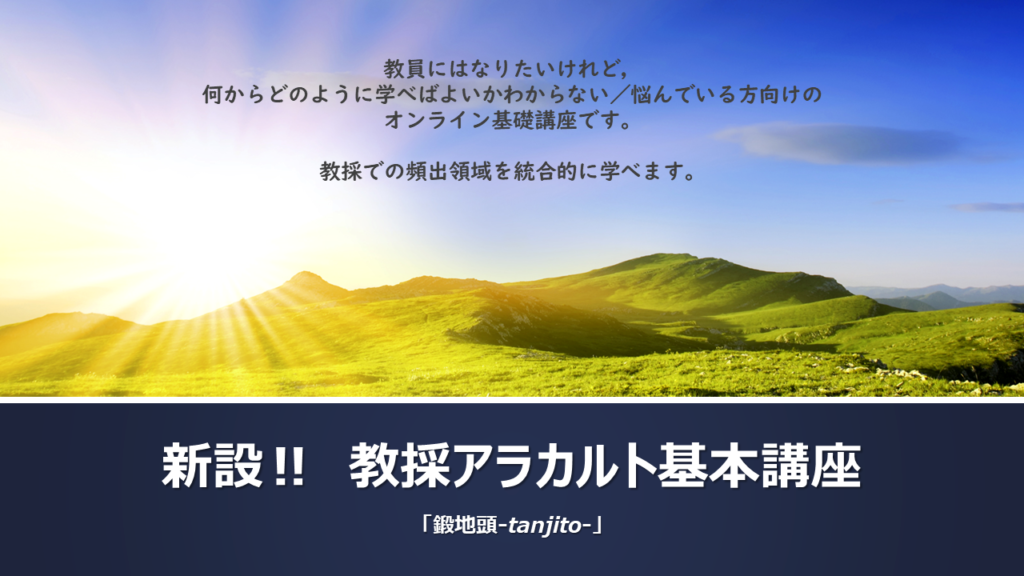
2 教採アラカルト(児童虐待)
出 題
問 担任するクラスの児童生徒が児童虐待を受けているのではないかと思われるが,確証がない。しかも,児童相談所(児相)に通告することは職務上知り得た秘密を漏洩することになるのではないかと躊躇われる。それでも通告すべきか?
ミニ解説・塾長の述懐・資料
常識的な出題です。教採の出題としては「通告義務」と「守秘義務」及び前二者の連関を法律等を根拠に解答すれば良いのです。
上記の出題に「通告すべきである」又は「通告すべきではない。」と自ら解答した上で,正解を確認して一喜一憂し,簡単な解説を読んで学習が終了する。これでは学習しないよりは増しですが,学習内容を身に付ける学習とは言えない。
当道場の場合,例えば,併せて児童虐待防止法の改正のポイントを整理する,長期欠席児童生徒への対応について議論し塾長の解説を聴くなどを行うのです。単に正解至上主義では特にこれからの〈新しい教育〉を担う教員の資質・能力は磨かれませんから。
次の資料は必ず読んでおきましょう。教採のレベルからすれば発展的な内容になるのかもしれませんが,学校現場では当たり前に知っておくべき内容です。
「教採アラカルト基本講座」を受講しておられる方のためのブログ教材です。
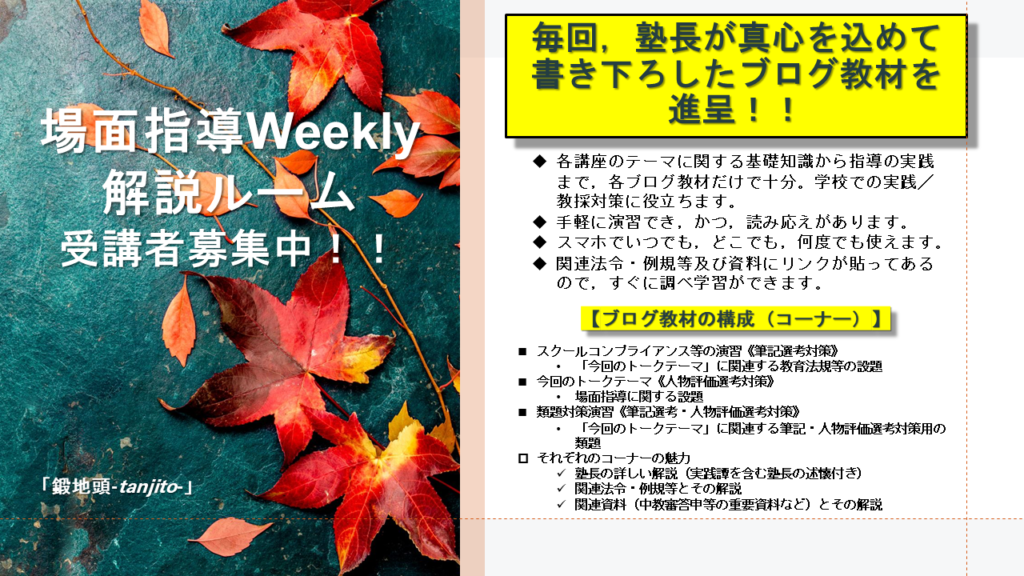
3 場面指導等(児童虐待・特番)
児童虐待19万3780件 全体・増加数とも過去最多 厚労省
昨日[1]令和2(2020)年11月8日,見出しにかかわる報道がありました。そこで,本コーナーを特番として,地元紙「中國新聞」(2020年(令和2年)11月19日(木曜日))の記事に沿い,厚生労働省のまとめたもの(速報値)を追ってみたいと思います。
教採では教育時事情報として取り上げられる児童虐待の相談件数です。前回調査(平成30年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数)の159,850件(速報値)を大きく上回る数値が返ってきますから「時事ネタ」としてはトピックなのでしょうが,単にトピックだから数値等を覚えるというだけの乏しい発想では教員の資質・能力に欠けるわけです。
少なくとも,――数値の裏側にある要因・背景は何か? 学校(教職員)として何ができるのか? ――こうした思考性で数値を追ってもらいたいと思います。
塾長の述懐
上記「厚労省のまとめ」で記述したこどもの前で家族に暴力を振るう心理的虐待「面前DV」の増加が気になります。同紙によれば,「加害者として「実父」が占める割合が年々上昇」し,「面前DV」の増加を底上げしたようです。
10月,茨城県ひたちなか市で起きた生後1か月の赤ちゃんの虐待死。逮捕された父親は「泣き声でストレスがたまった。」と供述,母親は虐待を制止できなかった理由として夫への恐怖心を語ったと報道されています。
また,当該の家族にかかわった自治体の母子保健担当者は虐待担当部署とも連携を図りながら,3度の家庭訪問を実施していますが,父親と面会できたのは1回のみ。母親からの相談も「夜泣きで夫も寝不足」に止まり,児相につなぐ判断に至らなかったとあります。
「お母さんと信頼関係を築けていなかったのかも。」
母子保健担当者の言葉だそうです。
飽くまでも新聞による報道(情報)ですが,こうした状況は他にも現実に生起しており,上述した事案は氷山の一角に過ぎません。推測ではありますが,数値に上がらない児童虐待が横行しているものと思われます。
さて,そこで,学校として,また一教職員として何ができるのか?
今回はこの問い掛けだけをもって擱筆したいと思います。

© 2020 「鍛地頭-tanjito-」
References