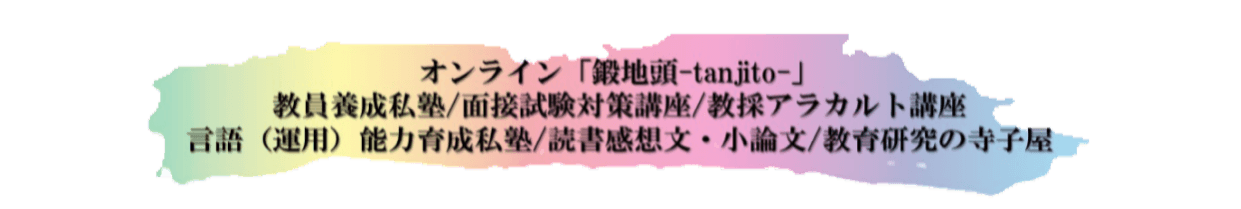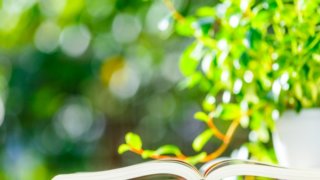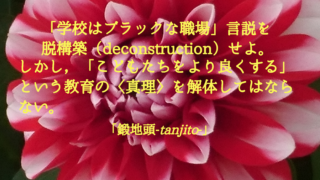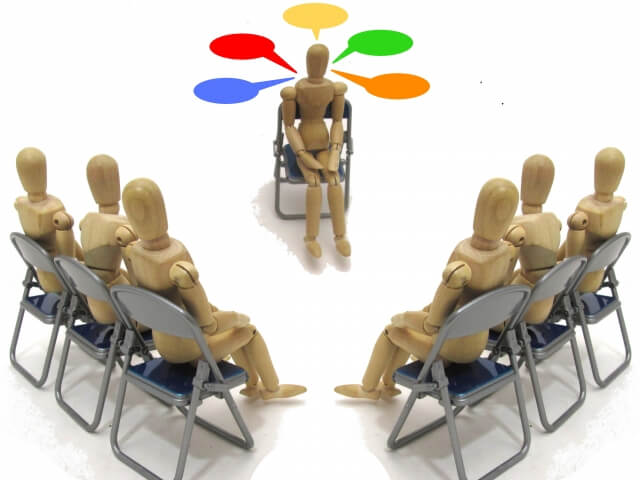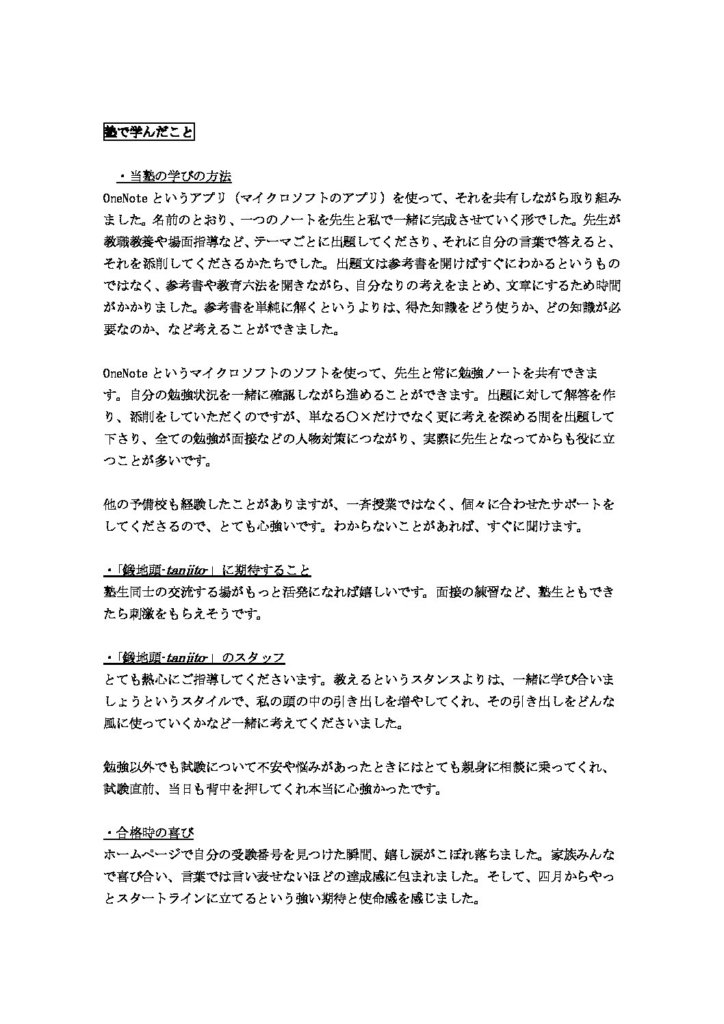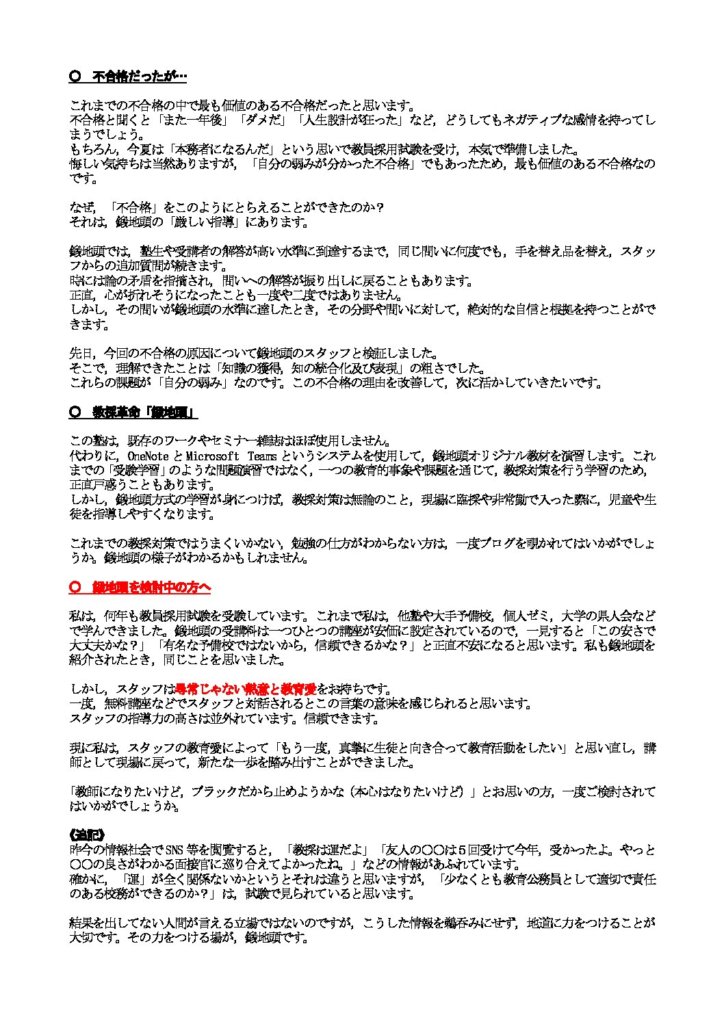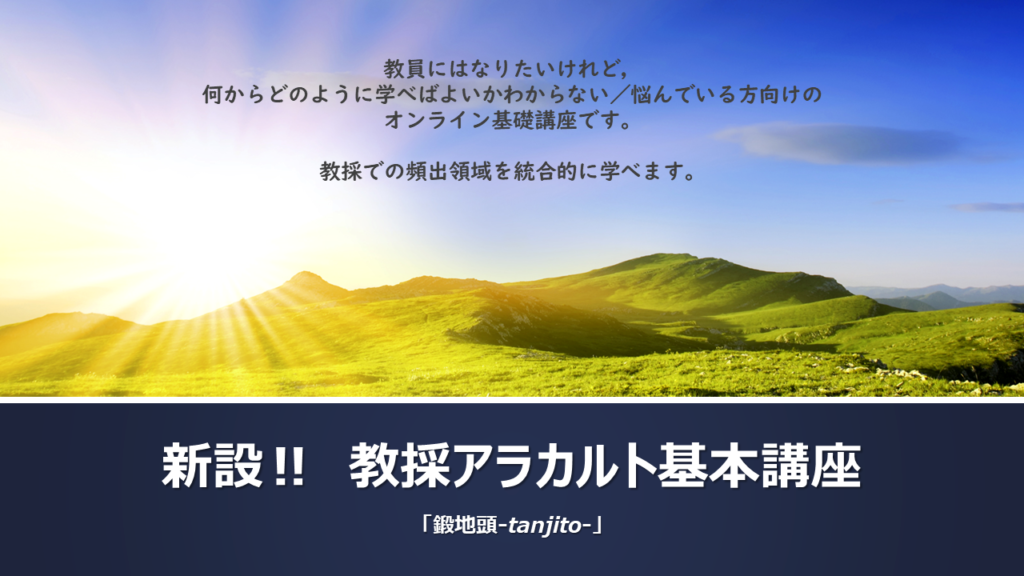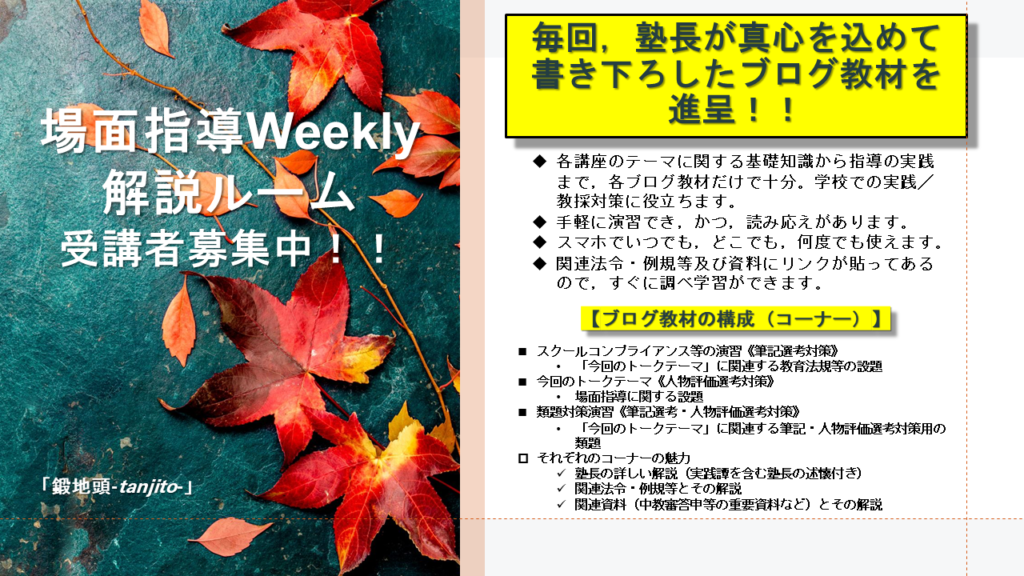Warning: Undefined array key "file" in /home/tanjito0201/tanjito.ne.jp/public_html/wordpress/wp-includes/media.php on line 1788
Warning: Undefined array key "file" in /home/tanjito0201/tanjito.ne.jp/public_html/wordpress/wp-includes/media.php on line 1788
0 テーマ
「信頼される教員」が
「信頼される学校」を創る!!
1 プロローグ
ちょっと前のこと,竹田青嗣氏の『現代思想の冒険』(ちくま学芸文庫,1992.6)を読んでいた時のことだ。――人生3度目に手にする書籍である。その度に「考える」とは何かについて考えてしまう。――
中途,当の書籍とは――全くとは言えないと思うが,――脳裡のスクリーンに再構築していたリニアの世界とは異なるある種の想念が,確かに脳裡の片隅に浮揚してきた。なぜ浮揚してきたのかは分からない。
「大量生産・大量消費の時代の終焉」
大量生産(・大量消費・大量廃棄)は環境問題を引き起こした。[1]参考:「はじめに」(環境省) 当然,問題解決の対象となる。一方で,消費の多様化の時代を迎えた昨今のキーワードは「パーソナライズ」や「モノを介した体験(価値)」である。
「教員の大量生産の時代は終わった。キーワードは「個別最適な〈学び〉」と「体験的な〈学び〉だ。」
教採受験界の話だ。因みに,当道場は教採受験産業に与しているとさっぱり思っていない。そう思っているのならば,利潤を目的に「教員の大量生産」を行っている。――全ての教採受験産業が利潤だけを目的としていると言っているわけではない。一般論として「大量生産」は利潤追求だ。ただし,このように述べると,「金が欲しいくせに,その言葉は嘘だ。」と心無い発言をする人間が必ず現れる。無論,労働の対価は必要だ。資本主義社会の中,生活をしなければならない。しかし,エゴイズムの象徴と思われる尋常ならぬ豪奢な生活などは一切必要ない。そんな妄想すら浮かばない。――「鍛地頭-tanjito-」はスタッフが寡少だ。そのようなことをしていては,将来のある乳幼児・児童・生徒の眼前に立つ教員の質が低下する。既に周囲にはそうした現状を危惧する声がある。「鍛地頭-tanjito-」自らが教員の質的低下を招く「大量生産」に加担することなど生理的に無性に嫌であり,当該の受験主体に対して甚だ無責任だとも思うのである。
「鍛地頭-tanjito-」の基本理念を理解した上で,道場の門を叩く受験主体と〈学縁〉を大切にし,一人ひとりの〈個性〉を尊重しながら,一人ひとりの教員としての〈資質・能力〉を引き出す。――それは学校現場で苦労に苦労を重ね児童生徒や教員を育ててきた人間の魂だ。――そのためには,一人ひとりの受験主体等ととことんかかわる。これは元教員として当たり前の姿である。いや,元教員だからこそできるのだ。
「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」
自身の人生を賭し,この基本理念をホンキで貫く〈ホンモノの教員〉を一人でも多く増やしたいだけだ。
この世にホンキでそう思っている人間はいるんだよ。
2 教採アラカルト(面接)
出 題
問 「信頼される学校」とはどのような学校のことですか?
塾長の述懐・資料
塾長の述懐
「有り触れた出題だなあ。」
「また,例の「てっぱんネタ」っていうやつか!?」
出題を一瞥し,瞬間的にこのように思ってしまったら,教員としての資質・能力は低いと思って良いです。完全に受験脳の判断です。学校現場で「信頼される学校」をそのように受験脳で捉えることなどできはしないのです。それほど重大なテーマなのです。
資料
地域に開かれ信頼される学校を実現するため,学校には,保護者や地域住民の意見や要望を的確に反映させ,家庭や地域社会と連携協力していくことが求められています。それと同時に,保護者や地域住民が,学校と共に地域の教育に責任を負うとの認識の下,学校運営に積極的に協力していくことも重要です。
「文部科学白書2008」(文部科学省,第2章 初等中等教育の一層の充実のために,第4節 信頼される学校づくりを目指して,1 自律的な学校運営に向けてー地域の参画を通してー,p.111)
そのため,学校が,地域や子どもたちの実情に応じて主体的に創意工夫のある教育活動を展開し,自主的・自律的な学校運営ができるよう,教育課程,予算などについての学校の裁量を拡大することが求められています。
また,保護者や地域住民の参画しやすい環境を整え,開かれた学校づくりを促進していくために,学校評議員制度や,平成16年度に導入されたコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)を活用していくことが重要です。
さらに,学校評価を通じ,学校が組織的・継続的にその運営の改善を図ることにより,保護者や地域住民に対する説明責任を果たすとともに,学校・家庭・地域の共通理解を深め,連携協力の促進を図り,また,学校の設置者などによる支援や条件整備などの改善を通じて,教育の質の保証・向上を図ることが期待されています。
これらの活動を通じて,保護者や地域住民に信頼される学校づくりを進めていくことが求められています。
塾長の述懐
当道場においても上記引用中の概念(術語)の足し算を行って,面接の解答とする塾生・受講者がおられます。だから,その方々とは「信頼される学校」についてじっくりと〈対話〉を持たせていただきます。なぜならば,解答として不足している,しかも「信頼される学校」の根幹となるものが複数不足しているからです。
無論,上記引用中の内容は大切です。
「大切なのならば,教採なのだからそのレベルで良いではないか!」
「そんな受験脳だけでは「信頼される教員」にはなれません。学校現場で苦労しますよ。…児童生徒が。保護者が。地域住民が。その後に,あなたが。」
3 場面指導等(保護者連携)
出 題
問 2人の保護者が来校し,担任のあなたに「先生,うちの子が先生のクラスに居たくないと言い続けます。担任を代わってもらえませんか。」と口々に言いました。あなたはどのように対応しますか?
塾長の述懐
「担任を代わって欲しい。」と保護者から直接言われて舞い上がるようでは「担任を代わって欲しい。」と言われても致し方ないでしょう。
担任に直接話すのではなく,管理職に直行したり,仲の良い(担任以外の)先生に胸の内を漏らしたりする場合がありますが,複数で直接本人に話したということになれば,保護者たちの抑えきれない気持ちが爆発したと考えて良さそうです。「クラスに居たくない」が不登校につながったらと思うと,保護者としては不安でならないのだと考えられます。
こうした事態に直面したとき,「何か自らの指導にミスがあったのか?」と直感的に思うことはあったとしても,――本当に自らのミスがあったのならば,誠意をもって素直に謝罪し反省することは当然ですが――それのみに囚われ続けるとしたならば,それは教員として冷静な対応とは言えませんし,以降,冷静な対応はできないでしょう。
「表象化した児童生徒に対する直接的な自らの指導のミス」の他に児童生徒が「先生のクラスに居たくない。」と発することに対して,想定できる要因・背景が(緊張を要するであろうこうした場面にあっても)複数,さっと脳裡に浮かぶくらいにならないと,それ以降を含め,十分な対応はできないはずです。――ただし,複数,さっと浮かぶような教員にはこうした「担任を代わって欲しい。」といった保護者の要望はないでしょう。「えっ? 何が言いたいんだ?」ですか? 「担任を代わって欲しい。」との要望を回避するといったレベルの問題ではなく,常日頃,さっと浮かぶ複数の視点を持ち,学級(ホームルーム)経営等に勤しむべきだと言いたいのです。さあ,その複数の視点とは…。当該の担任が回収されてしまったかもしれないピグマリオン効果もその一つかもしれない…。まあ,じっくり調べ,考えてみてください。そうすれば,巷間の参考書には書かれていない,教採ならば,面接官を唸らせる解答に行き着くはずです。そう祈ります。ただし,それらの解答はプロの教員ならば,日常的に実践できていないといけないものです。――
思考が混乱しそうですか? そうならば,このような訴えを受けたとき,まず最初に何をしなければならないのでしょうか。原点に立ち返りましょう。それは鉄則と言えるものです。
ここから調べ,考え始めましょう。
続きは「場面指導Weekly解説ルーム」で。
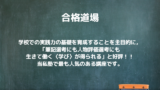

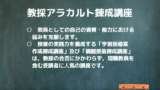

© 2020 「鍛地頭-tanjito-」
References